Netpress 第2469号 適法と判断されるには? 「試用期間の延長」と 「本採用拒否」に関する考え方

1.新入社員の能力不足や企業側の都合等により、試用期間の延長や本採用拒否を検討することがあります。
2.こうした場合、どのような要件を満たせば期間の延長や本採用の拒否が認められるのかについて解説します。
1.試用期間とは
試用期間とは、法律上の定義はありませんが、採用した労働者の能力や適性を見極めるため、本採用前に設けられている一定の期間をいいます。
試用期間の長さについて、法令の定めはありませんが、能力等の見極めのために必要とされる合理的な期間を超えた長期の場合には、公序良俗違反により無効とされる可能性があります。一般的には、3か月から6か月程度の期間で定められることが多いとされています。
試用期間の法的性質については、解約権留保付(企業側が解雇の権利を留保した状態)の雇用契約であるという考え方が確立されています。
2.試用期間の延長が認められるケース
新入社員の本採用の可否を決めるために、もう少し時間がほしい場合や、配属した部署以外での適性を見極めたい場合等に、企業としては試用期間の延長を検討することが考えられます。
この点、試用期間の延長について定めた法令はありませんが、試用期間の目的や、試用期間中の労働者が不安定な地位に置かれることを考慮すると、無制限に延長が認められると解するのは合理的ではありません。
具体的には、以下に述べるような要件が必要と解されます。
(1) 試用期間の延長について、就業規則等に根拠があること
試用期間を延長することは、労働者にとっては労働条件の不利益な変更に当たり得るため、就業規則や雇用契約書において、延長に関する規定が必要と解されます。
就業規則や雇用契約書に定めがない場合には、労働者から延長について個別に同意を得たとしても、延長自体が「就業規則で定める基準に達しない労働条件」となり、原則として無効となります(労働契約法12条)。
この点について、就業規則や雇用契約書に延長に関する規定がなくても、やむを得ない事情があると認められる場合、労働者の同意を得たうえで、必要最小限度の期間について試用期間を延長することは同条に違反しないとする裁判例もあります。しかし、トラブル回避の観点からは、延長について就業規則等で定めておくべきです。
(2) 延長が認められる合理的な理由があること
就業規則や雇用契約書に試用期間の延長に関する定めがあったとしても、延長が認められるためには合理的な理由が必要で、その期間も合理的な範囲に留める必要があります。
また、当初の試用期間を超える期間について延長する場合には、その一部が、必要性が認められない等の理由で無効とされる可能性があります。
3.試用期間の延長が無効とされるケース
試用期間の延長について求められる要件を満たさず、有効性が認められない場合には、試用期間の延長にかかわらず、当初の試用期間の満了日の経過により、労働者との雇用契約は、解約権留保のない通常の労働契約に移行することになります。
したがって、後日、企業側が行った本採用拒否は、労働契約法16条等に照らし、採用後の労働者に対する「普通解雇」として有効性が認められるかどうかを検討することになります。
4. 雇用契約を終了することができるケース
試用期間の満了後、労働者を採用しないという判断に至ったときに、どのような場合に本採用を拒否できるのかが問題となります。
この点、前述のように試用期間は解約権留保付の雇用契約と解されているところ、このような解約権留保は、一定期間内で労働者の適性を見極めたうえで最終的な採否決定を留保する趣旨でなされていると考えられることから、採用後の労働者と比較すれば、広い範囲における解雇の自由が認められるとされています。
もっとも、本採用の拒否が無制限に認められるわけではなく、「解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認」されなければなりません。
また、労働契約の締結当初には知ることができず、なおかつ、知ることが期待できないような事情を知るに至った場合を除いて、本採用の拒否は許されないとされています。
以上を踏まえたうえで、試用期間後に雇用契約を終了することができるケースをみていきます。
(1) 新卒またはこれに準ずる労働者の場合
新卒またはこれに準ずる労働者については、能力不足や勤務態度等に問題があったとしても、直ちに本採用を拒否することは許されないと考えるべきです。
新卒等の労働者については、社会人経験も乏しく、問題点に対する適切な注意喚起や指導により改善が期待できる場合も少なくありません。
そのため、面談等を通じて問題点を具体的に指摘して改善の機会を与えたり、改善の有無等に関する企業側の認識を伝えたりするなど、企業側が問題点に対して適切な指導を実施することが必要です。
それでも改善の見込みが立たない場合には、本採用拒否に合理的な理由が認められると考えられますが、一方で、企業側がこのような取り組みを行っていない場合には、本採用拒否が違法と判断される可能性があります。
(2) 中途採用者の場合
中途採用者の場合、実務経験や特定の能力を有し、即戦力として業務に携わることが期待されている場合が多いといえます。
そのため、試用期間中にそうした能力等の不足が明らかになった場合には、新卒者等と比較すると緩やかな要件で本採用拒否が認められると解されています。
もっとも、緩やかとはいえ、原則として、面談等を通じて中途採用者に対する指導や改善についての取り組みを行う必要があると考えられます。
裁判例のなかには、試用期間中の問題点改善に向けた指導が十分になされたとまではいえない場合でも、本採用拒否を適法と認めた事例もあります。
しかし、やはり面談等でそのような指導を行ったほうが、中途採用者の了解を得て合意退職という形につなげやすくなり、最終的に本採用拒否に至った場合に、適法と認められる可能性が高まると考えられます。
◎協力/日本実業出版社
日本実業出版社のウェブサイトはこちらhttps://www.njg.co.jp/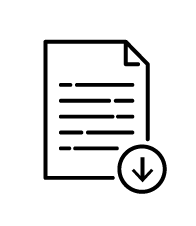
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




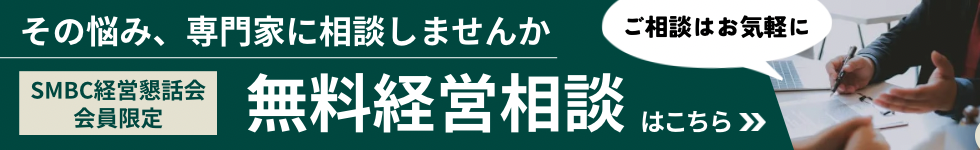

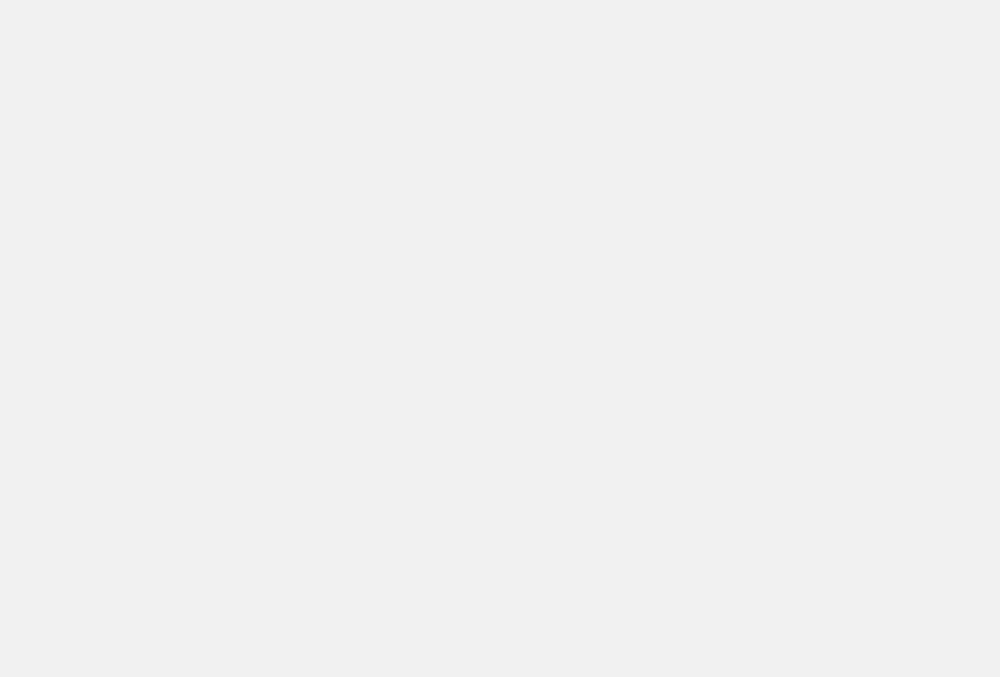

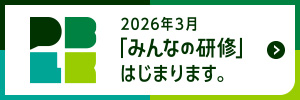




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
