Netpress 第2488号 被害が深刻化 「就活セクハラ」対策が事業主の義務になる!
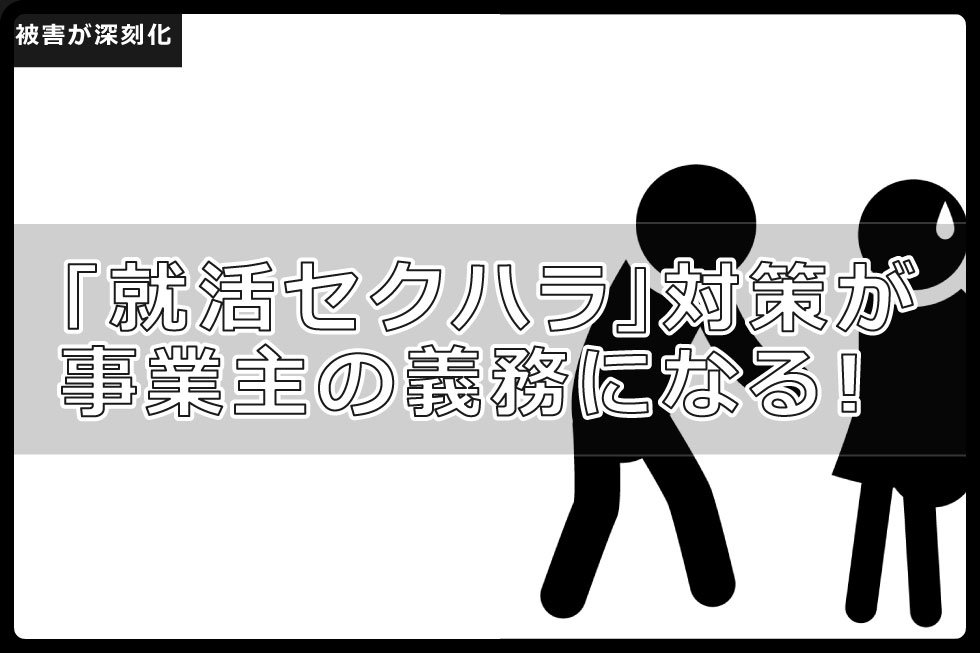
1.法改正により、就活セクハラを防止するための対策が、2026年にも労働施策総合推進法上の義務となります。
2.就活セクハラがもたらすリスクを確認したうえで、その防止策やルールの定め方について解説します。
1.「就活セクハラ」対策が事業者の義務に
近年、「就活セクハラ」(就職活動中またはインターンシップ中の学生に対するセクハラ)の被害が深刻化しています。
このような現状を受けて、ことし6月11日に労働施策総合推進法等の改正法が公布されました。施行日は、公布日から起算して1年6か月以内の政令で定める日です。
これにより、就職活動中の学生やインターンシップ生等に対して、セクハラを防止するために必要な措置を講じることが事業主の義務とされます。
具体的には、「事業主の方針等の明確化とその周知・啓発」「相談体制の整備・周知」「発生後の迅速かつ適切な対応」などが挙げられ、今後さらに指針において示される予定です。
2.就活セクハラがもたらすリスク
就活セクハラは、ハラスメントを受けた学生に大きな心理的ダメージを与えるだけでなく、企業と行為者にも重大なリスクをもたらします。
(1) 企業のリスク
企業のリスクとしては、社会的信用を失い、企業イメージが低下します。就職後の職場でもセクハラが横行していると認識され、応募が減少する可能性もあります。
また、従業員の意欲低下にもつながり、人材の退職・流出が起きやすくなります。
(2) 行為者のリスク
加害者である当該従業員には、被害者からの慰謝料の請求など民事上の責任が生じます。さらに不同意わいせつ罪(刑法176条)や不同意性交等罪(刑法177条)といった刑事上の責任が問われる可能性もあります。
また、社内においても、けん責、減給、出勤停止、論旨解雇、懲戒免職といった処分を受ける可能性があります。
3.企業に求められるセクハラ防止策
企業としては、従業員に対するセクハラ防止策と同様に、就活セクハラの防止策を講じる必要があります。
就活セクハラに対して、具体的な取り組みがなされていない中小企業は少なくありませんが、就活セクハラ問題はすでに深刻化していることから、「法律の施行日までに対応する」のではなく、早急に防止策を講じるようにしましょう。
就活セクハラの防止策は、従来のセクハラ防止策を基本として、就活特有の事情を考慮して策定します。
(1) 方針の明確化・周知徹底
まずは、全従業員(特に採用担当者)に対し、就活セクハラを含む、すべてのハラスメントを禁止する方針を明確化します。さらに、就活ハラスメントを行った場合に、その行為者を処分する社内規程や規則を設け、周知します。
(2) 研修・教育の実施
採用担当者を含む全従業員に対し、セクハラ防止に関する教育や研修を実施します。まず、社内でセクハラとなり得る言動を就活生に行えば、就活セクハラとなることを伝え、そのうえで、採用活動において、どのような言動がセクハラとなるのか、どのような場面で起きているかについて、具体例を挙げるとわかりやすいでしょう。
また、セクハラだけでなく、立場の弱い学生の尊厳や人格を不当に傷つけるなどの就活ハラスメントも許されない行為であることを伝えます。
そのうえで、前述した就活セクハラのリスクを伝え、実際に就活セクハラを起こした従業員にどのような処分が下されるかを説明しましょう。
(3) ルール作成のポイント
就活セクハラを防止するには、学生と接する際のルールをあらかじめ定めておくことが重要です。
ルールを作成する際には、正式な採用活動のみならず、OB・OG訪問やSNS、就活マッチングアプリなども想定しましょう。特に、就活マッチングアプリはトラブルのきっかけになることもあり、利用自体の禁止を検討する必要もあります。
ルールの内容を従業員に告知し、就活セクハラを含むハラスメント行為をしないと誓約書に署名をさせることも意識醸成と抑止力につながります。さらに、これらの社内ルールを学生に対して公表してもよいでしょう。学生の安心感や信頼感、人材獲得にもつながります。
(4) 相談窓口の設置・運営
学生向けの相談窓口を設置し、学生に周知しましょう。この相談窓口は、可能であれば人事部の管轄とは別に設置します。そうすることで、学生は採用で不利になることを心配せずに相談しやすくなります。
4.就活セクハラが起きてしまったら
就活セクハラが起きてしまった場合の対応の流れは、基本的に社内セクハラの場合と同様です。
(1) 事実確認
就活セクハラの相談・報告を受けたら、被害者のプライバシー保護を前提に、迅速かつ適切に事実確認を行います。
相談を受ける際は、誠実な姿勢で話に耳を傾けます。相談者の同意を得たうえで、行為者とされる人物や関係者へのヒアリングを行いましょう。
また、「名前を伏せてほしい」という相談者もいます。相談内容をどこまで開示するかについても擦り合せが必要です。
行為者とされる人物へのヒアリングも、「相談があり、関係部署の人たちに話を聞いています。あなたにも事情を伺いたいのですが」と協力を依頼するような伝え方をしましょう。ヒアリングは、懲戒手続ではなく、事実関係を確認するために行うものだからです。
(2) 被害者の救済
就活セクハラが事実と確認できた場合、会社による被害者への謝罪など、速やかに被害者への救済措置を行います。
(3) 措置の実施
就業規則等の懲戒規定に基づき、行為者に対して必要な措置を行うとともに、社内において就活ハラスメント防止に関する方針の周知徹底を図るなど、就活ハラスメントの再発防止策を徹底します。
(4) 公表
就活セクハラの事実が深刻と判断した場合は、社外への公表を検討します。実際に公表する場合には、被害者から公表について承諾を得たうえで、被害者のプライバシーに万全の配慮を行うことが必要となります。
◎協力/日本実業出版社
日本実業出版社のウェブサイトはこちらhttps://www.njg.co.jp/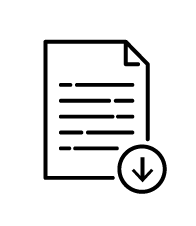
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




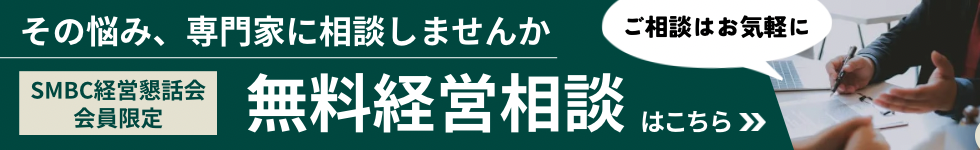

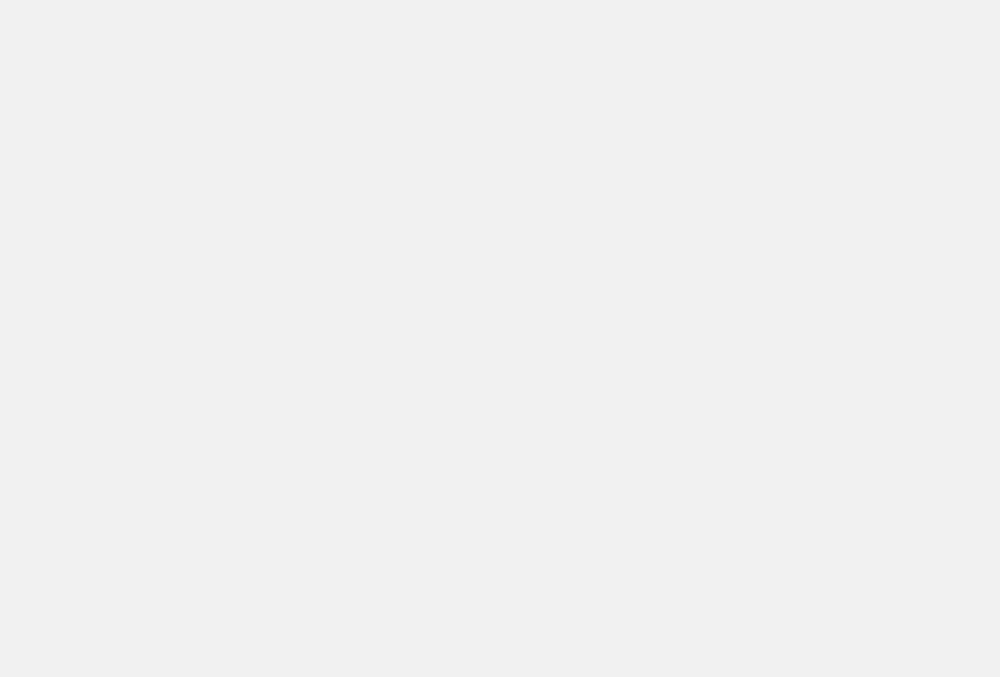

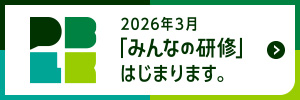




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
