Netpress 第2487号 元国税調査官が教える 「税務調査」の現在地と企業に求められる対応策

2.次世代システムの導入など最新の税務調査の動向と、企業に求められる対応策について解説します。
1. 税務調査の「現在地」と変化する調査現場
コロナ禍の影響で一時的に減少していた実地調査件数は、近年、回復傾向にあります。
実地調査に限らず、書面照会や電話による連絡、来署依頼による面談など、簡易な接触も増加しています。
2024年6月末時点の法人数は約340万社あり、2023事務年度における法人税・消費税の実地調査の件数は約5万9,000件でした。単純計算で調査実施率は全体の約1.7%となります。さらに、簡易な接触については約7万件あったことを踏まえると、全体の約3.8%の法人に対して、何らかの接触があったと推定されます。
調査対象となる法人の選定は、過去の申告・調査事績、業種別の指標における異常値などをもとに行われています。
グローバル化の進展により租税回避の手口が複雑化していることから、個人・法人をまたいだ税目横断的な調査も行われるようになっています。
2. 次世代システムの導入
国税庁では、2026年に現行の国税総合管理システム(KSK)を全面的に刷新し、次世代基幹システム(KSK2)の運用を開始する予定です。KSK2の主な特徴は、次の3点です。
① すべてがデータ化される・・・従来の税務署業務は紙を中心に処理されてきましたが、KSK2ではすべての情報がデジタル化され、電子的な事務処理が基本となります。
② 納税者情報の一元管理・・・これまで、税目ごとに個別管理されていた「法人税」「所得税」「消費税」「相続税」などの情報が統合され、納税者ごとの全体像を横断的に把握・分析できるようになります。
③ リアルタイムで情報にアクセス可能・・・従来は調査官がKSKの情報を紙に出力して持ち出していましたが、KSK2では税務署外からでもシステムにアクセスでき、インターネット上のデータとも連携した情報分析が可能になります。このシステム刷新により、税務調査の選定方法や進め方が大きく変化することが予想されます。
3. 会計ソフトにまつわる調査と留意点
インボイス制度の導入や補助金制度の後押しなどもあって、会計ソフトを利用する事業者が増加しています。
銀行口座明細やクレジットカード明細の自動取り込み、請求書データとの連携などにより、経理業務の自動化・効率化が進んでいます。
しかし、「会計ソフトを使っているから安心」というわけではありません。自動仕訳や学習機能により、誤った科目に自動登録されるリスクや、計上時期の判断を伴わない処理がなされることもあります。設定ミスが連鎖的なミスを引き起こすこともあるため、定期的な内容の確認と見直しが不可欠です。
たとえば、交際費のつもりで処理した支出が実際には寄附金と判断され、法人税では損金不算入となり、同時に消費税の仕入税額控除も否認されたというケースがあります。
国税局や税務署には、会計ソフトに精通した情報技術専門官が配置されており、仕訳帳データをCSV形式などで提出させ、たとえば期末・決算後の入力、訂正、削除履歴などを分析しています。
従来は税務調査の臨場後にデータを提出させていましたが、近年は調査前にデータを提出させ、データ分析を経て調査項目を絞り込んでから臨場するケースが増えています。
海外では、クレジットカード取引データが税務当局に自動送信され、調査資料として活用されている国もあります。日本はその分野において遅れをとっているものの、将来的には電子商取引の拡大とともに、会計データや取引データに基づく「分析型調査手法」が主流になる可能性があります。
4. AI税務と調査
AIを用いた調査対象の選定は、従来のロジックベースや調査官の経験・勘に頼る方法に比べて、より広範で複雑なパターンに対応できる点で期待されています。国税庁内で保有しているデータのみならず、インターネット上の公開情報やSNS、業種の特性なども判断材料として分析に役立てている可能性があります。
しかし、調査現場の実情として、AIが選定した法人について、「なぜこの法人が選定対象になったのか」が調査官にもわからない場合があり、結果として調査対象から除外されることもあるといわれています。
実際には、好況法人、売上規模が一定以上の法人、現金取引の多い業種など、従来から注目されてきた層が引き続き調査対象とされる傾向は、大きく変わっていないと考えられます。
なお、AIによって「不審」と判定された事項が、必ずしも申告漏れや不正に直結するわけではありません。
仮に調査対象となった場合には、自社の業務フローや記帳内容、内部管理体制を見直す好機と捉え、調査結果を今後の業務改善に活かす姿勢が重要です。
最後に、税務調査時に調査官が着目する主なポイントを下表にまとめたので、参考にしてください。
| 項 目 | 調査官が着目する主なポイント | チェック欄 |
| 売上 | 自社の売上計上基準に基づいて適切に売上を計上しているか | □ |
| 原価 | 棚卸資産の数量、金額は適正か | □ |
| 役員報酬・人件費 | 経済的利益や過大給与はないか | □ |
| 事前確定届出給与が届出どおりに支給されているか | □ | |
| 交際費等 | 交際費以外の科目に交際費等に該当するものはないか | □ |
| 1人10,000円以下の飲食費用の損金算入は適正か | □ | |
| 固定資産 | 取得価額に含めるべき付随費用を損金処理していないか | □ |
| 資産の取得時期・耐用年数・償却方法は適正か | □ | |
| 個人的経費 | 業務に無関係な費用を損金計上していないか | □ |
| 消費税 | 不課税、非課税、免税の取り扱いが適切か | □ |
| 帳簿の記載や請求書等の保存を適切に行っているか | □ | |
| 源泉所得税 | 各種手当や経済的利益の課税漏れはないか | □ |
◎協力/日本実業出版社
日本実業出版社のウェブサイトはこちらhttps://www.njg.co.jp/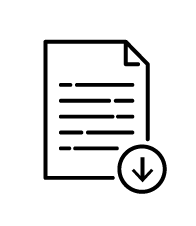
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




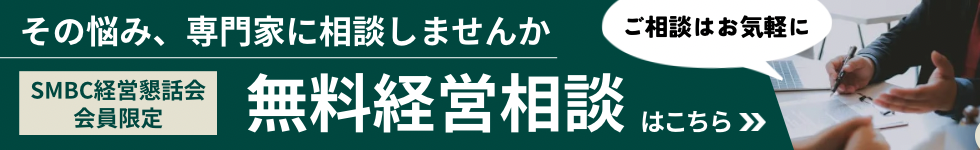
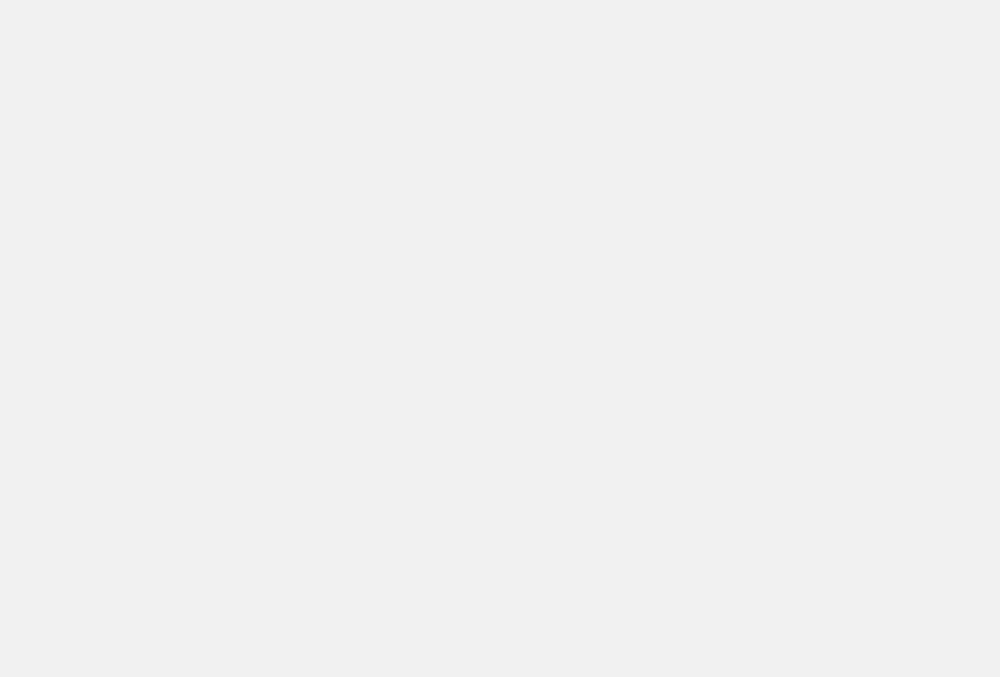

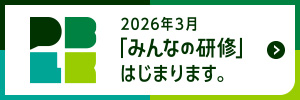




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
