Netpress 第2445号 Quiet Quitting 「静かな退職」にどう備えればよいか

1.「静かな退職」とは、昇進や成長を追わずプライベートを優先する働き方で、背景には会社への不満や評価の欠如があります。
2.無理な異動などで状況を悪化させるより、「静かな退職」を生む原因そのものを解消することが組織改善の鍵です。
3.出世以外の多様なキャリアパスを提供するなど、組織の生産性を高める「静かな採用」の実施が解決策になるでしょう。
1.静かな退職を選べる「無欲な」人たち
若者世代を中心に広がっているという「静かな退職」。要は、決められたこと以外の仕事をせず、仕事面での昇進や成長を目指さない働き方です。その分プライベートを充実させることが、いまどきのコスパとかタイパの良い生き方だ、ということになるのでしょうか。
「若者世代を中心に広がっている」といいましたが、静かな退職者はどの世代にもいるはずです。たとえば、次のような人たちです。
・30代で管理職になることを、割に合わないと判断した人
・40代で趣味を優先するようになった人
・50代で役職を外れてやる気をなくした人
・60代で再雇用となり給与と責任が減った人
誰しもが、会社に対する期待をなくしたとき、静かな退職を選びます。
ただ、それは今以上の生活を得ることを否定した生き方なのかもしれません。
もちろん副業という選択肢もあって、給与をもらっているメインの会社では静かな退職者になるけれど、副業には精を出す、という生き方もあるでしょう。
ただ、副業で稼ぐ人は少数派で、生活水準を引き上げるほど稼げる人はほんの一握りです。そうであれば、会社が定めた月給の範囲で静かに暮らすことを選ぶ、ということになります。それは、とても欲のない生き方を選ぶということではないでしょうか。
2.会社としてどう向き合うべきか
では、このような人たちに会社としてはどのように向き合うべきでしょうか。
決められた仕事だけやる、ということを否定的に見るのであれば、多忙な部署への異動を指示するということはありかもしれません。
静かな退職を選ぶくらいですから、積極的に転職活動をするような人たちではないのでしょう。
しかし、多忙な部署に異動させたにもかかわらず、静かな退職者が働き方を変えないとすれば、部署の他の人たちが忙しくなるだけかもしれません。
そもそも静かな退職者が生まれる背景には、仕事中心の生き方への反発だけでなく、仕事に見合った報酬がないことや、努力などへの評価がないこと、人間関係などへの不満があるといいます。会社への不満が高まり、期待がなくなった状態です。
これをエンゲージメントが低下した状態だということができます。ちなみに日本は、各種統計で、会社に対するエンゲージメントが一番低い国だともいいます。
つまり、静かな退職者に非があるのではなく、彼らを生み出す会社に非があるということです。
そんな状況で、さらにエンゲージメントを下げるような人事異動は、まだ頑張っている他の社員をも、静かに退職させてしまうかもしれません。
それはあまり得策ではないでしょう。
3.静かな退職を生んでいる原因に手を打っていく
会社によっては、静かな退職者が40%を超えているという場合もあるといいます。
経営者が言う「うちの社員はまじめだけれど言われたことしかしない」という状況を思い浮かべてみましょう。まさにそれが静かな退職者だらけの状態です。
しかし、そのような状況でもビジネスが回っているのであれば、もしかすると静かな退職への対策はとらなくてもよいのかもしれません。
静かな退職というキーワードが広がったのは、その対義語であるハッスルカルチャーへの反発であり、たくさん働いてたくさん稼いで良い生活をしよう、という元気な文化の国々でのことだからです。
24時間戦うことが死語になっている日本の企業では、会社への期待がない静かな退職者との相性はむしろよいかもしれません。
しかしながら、もし会社として成長を目指したいのであれば、何らかの対策をとるべきです。
それは、静かな退職を生んでしまう原因となっている様々な社内の課題を解決していくことです。エンゲージメントサーベイや社内ヒアリングなどから、課題とギャップを明らかにして対策を検討しましょう。
たとえば、ある会社では、2年目から4年目くらいの社員でやりがいが低下しているというエンゲージメントサーベイの分析結果がありました。そこで社内だけでなく社外での人とのネットワーク強化に取り組み、大幅な改善を実現することができました。この会社では、若手の指導は主に同じ部署の先輩や上司に頼っていました。けれども若手が望んでいたのは、むしろ社外の様々な人との出会いだったのです。
別の会社では、中堅社員に対して、社内で認められて出世することだけでなく、専門性を高めて社外で認められることを促したり、出世以外のキャリアパスを用意したりすることで対策できた例もあります。
さらに別の会社で、高齢層に対する後ろ向きかつ十把一絡げでのアンラーニングやリスキリングを取りやめ、それぞれの個性や経験に応じた役割付与と自発的学習の補助などを進めました。
そのような既存社員の活性化を「静かな採用」と定義します。
会社がしっかり対策をとらなければ、「静かな退職」によって組織としての生産性を失うことになります。しかし対策をとることができれば、社員に対して新しいスキルや経験を与えることができ、組織として高い生産性を獲得することができるのです。
「静かな退職」ではなく、「静かな採用」に向けた取り組みをぜひ進めていきましょう。
日本実業出版社のウェブサイトはこちら https://www.njg.co.jp/
【SMBC経営懇話会会員限定】
SMBCコンサルティングの顧問のコンサルタントによる無料経営相談のご案内
| セレクションアンドバリエーション株式会社はSMBCコンサルティング株式会社の顧問のコンサルタントです。 SMBC経営懇話会会員向けの人事に関する無料経営相談を受けております。 無料経営相談の申込はこちら |
SMBC経営懇話会のサービスはこちらをご覧ください
SMBC経営懇話会のご案内
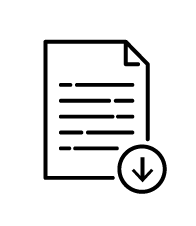
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




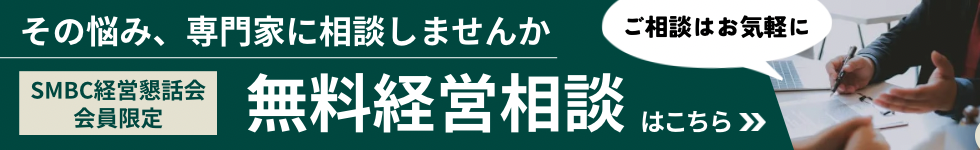

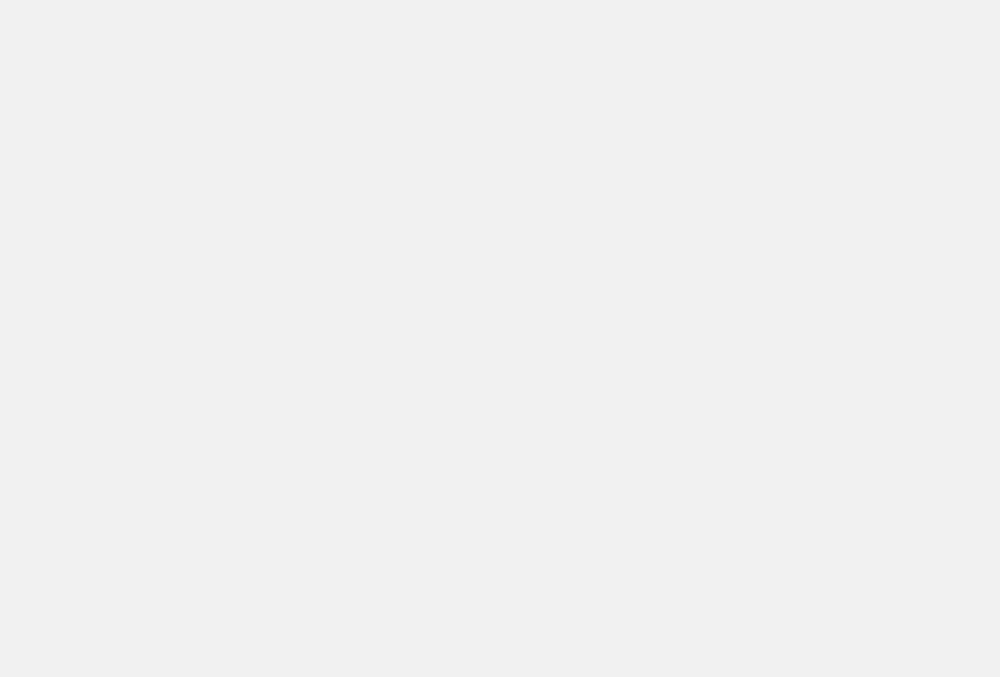

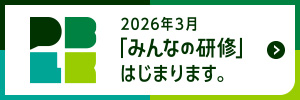




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
