Netpress 第2485号 なぜ変わらないのか・・・ 「組織変革」の進め方と 阻害要因への対処策

1.組織は時代とともに変革が求められますが、一向に変わることができない組織は少なくありません。
2.ここでは、あるべき姿へと変わるための組織変革の進め方と阻害要因への対処策について解説します。
1.組織変革の必要性
市場環境や技術が急速に変化し、従来の成功モデルが通用しなくなるなか、組織も変化に適応しなければ企業の持続的な成長を実現できません。
また、社員の価値観や働き方の多様化により、従来の管理手法ではモチベーションや生産性を維持することが難しくなっています。そのうえ、旧態依然とした上から目線のコミュニケーションや、経験や勘を重んじる意思決定では、セクショナリズムが蔓延し、組織どころか事業の変化や変革も進みません。
そこで、組織内のコミュニケーションや意思決定のあり方を見直し、柔軟で創造的な文化を醸成することが求められます。変革を先送りすれば、組織は徐々に硬直化し、市場での競争力を失いかねません。
したがって、組織変革は「必要に迫られて行うもの」ではなく、「未来を切り拓くために主体的に取り組むもの」と捉えることが大切です。
2.組織変革の進め方
組織をよい方向に変革し、組織文化として定着させていくためには、単なるスローガンやルールの策定だけでは不十分です。組織全体が価値観を共有し、それを日々の業務に落とし込むプロセスが求められます。
以下、そのステップを5つのフェーズに分けて説明します。
◆第1フェーズ・・・「危機感の醸成」
組織変革を成功させるためには、まず社員が「なぜ変わる必要があるのか」を理解し、納得することが不可欠です。
そのための最初のステップが「危機感の醸成」です。この段階では、組織の現状や課題を明確にし、社員と共有することで、変革の必要性を認識させます。
具体的には、アンケート調査やインタビューを実施し、組織の隠れた問題やその真因を可視化します。その結果を社員に公表し、現在の組織の姿と理想の姿のギャップを明示することで、「このままではいけない」「変わる必要がある」という機運を醸成します。
特に、現場のリアルな声を反映させることで、危機感が他人事ではなく「自分ごと」として認識されることが重要です。
◆第2フェーズ・・・「方向付け」
危機感を持った後は、組織がどの方向に進むべきかを明確にするフェーズです。経営層がビジョン示し、どのような価値観を組織に根付かせたいのかを定めます。
この過程で、理想の人物像や行動指針を策定し、それを経営層自らが発信します。
ただし、単に「こうあるべきだ」と一方的に伝えるのではなく、社員と対話をしながら共につくり上げる姿勢が重要です。目指すべき方向性を明確にし、組織全体の足並みを揃えることで、文化醸成の基盤を築きます。
◆第3フェーズ・・・「共感形成」
組織の価値観に対する社員の共感を生み出します。人は、納得しないものに対しては積極的に行動しません。そのため、この段階では、社員が「この行動は自分にとって意味がある」と感じられるような働きかけが必要です。
具体的には、ワークショップやディスカッションを通じて、「なぜこの組織文化が必要なのか」「自分たちの仕事にどう影響するのか」を考えさせる機会を設けます。
また、成功事例や過去の失敗事例を共有することで、組織文化の重要性を実感させることも有効です。経営層やリーダー層が率先して実践することで、社員の共感を得やすくなります。
◆第4フェーズ・・・「実践と定着」
共感が生まれた後は、実際に新しい価値観に基づいた行動を促進し、日常業務に定着させるフェーズに移行します。このフェーズでは、行動指針を形骸化させないための仕組みづくりが鍵となります。
たとえば、評価制度を見直し、組織文化に沿った行動を評価対象に加えることで、社員が組織文化を実践する動機を高めます。
また、管理職が積極的にフィードバックを行い、行動変容をサポートすることも重要です。定期的な1on1ミーティングなどを活用し、社員の取り組みを振り返りながら、よい行動を継続的に促していきます。
◆第5フェーズ・・・「組織文化へ」
最後のフェーズでは、取り組みを一過性のものにせず、組織の制度やプロセスに組み込み、持続的に発展させる仕組みを整えます。
たとえば、組織の評価制度や研修プログラムに組織文化の要素を組み込むことで、新入社員からベテラン社員まで一貫した価値観を共有できるようにします。
また、組織文化は固定的なものではなく、社会や市場の変化に応じて進化させる必要があります。定期的な振り返りを行い、社員のフィードバックを取り入れながら組織の成長と共に組織文化をアップデートしていくことが重要です。
3.変革を阻害する要因への対処策
組織開発においてよく取り上げられるのが「氷山モデル」です。たとえば、「社員が会議で意見を述べない」という問題が生じているとします。氷山の上で見えているのは「意見を述べない社員」ですが、その氷山の下には「意見を言うとすぐに社長に反対される・怒られる」「部署間のセクショナリズムが強く意見を言いにくい」など、目に見えないより大きな問題が隠れていることが多いものです。そのため、根本的な改革を進めるためには、表面的な対策に終始することなく、氷山の下に隠れている真の課題に踏み込む必要があります。
また、組織内の慣習や暗黙のルールも変革を阻む要因の1つです。「このやり方が当たり前」「うちの会社では昔からこうしてきた」といった固定観念が根強く残っていると、新たな取り組みに対して抵抗が生じます。特に、経営層や管理職が従来の成功体験に固執してしまうと、変革に向けた議論すら進まなくなります。
それから、組織のメンバーが「変わること」に対して不安や恐れを感じることも、変革を阻害する要因となります。「変革によって自分の立場が危うくなるのではないか」といった心理的抵抗が生じると、現状維持の力が働きます。その結果、改革の必要性は理解していても、実際の行動にはつながらないジレンマに陥ります。
このように、組織が変われない理由は、制度や仕組みの問題に加えて、深層にある価値観や心理的要因にも起因することが多いのです。だからこそ、組織変革を成功させるためには、阻害要因を理解したうえで、組織の深層に潜む「変われない理由」に向き合い、丁寧に対策を打っていくことが大切になります。
◎協力/日本実業出版社
日本実業出版社のウェブサイトはこちらhttps://www.njg.co.jp/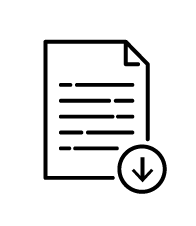
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




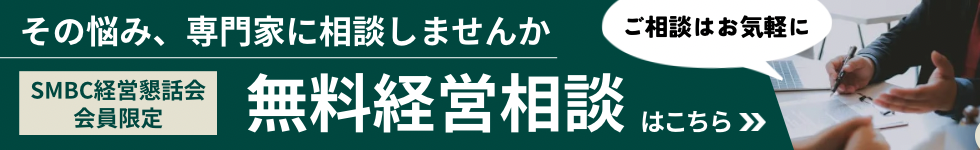
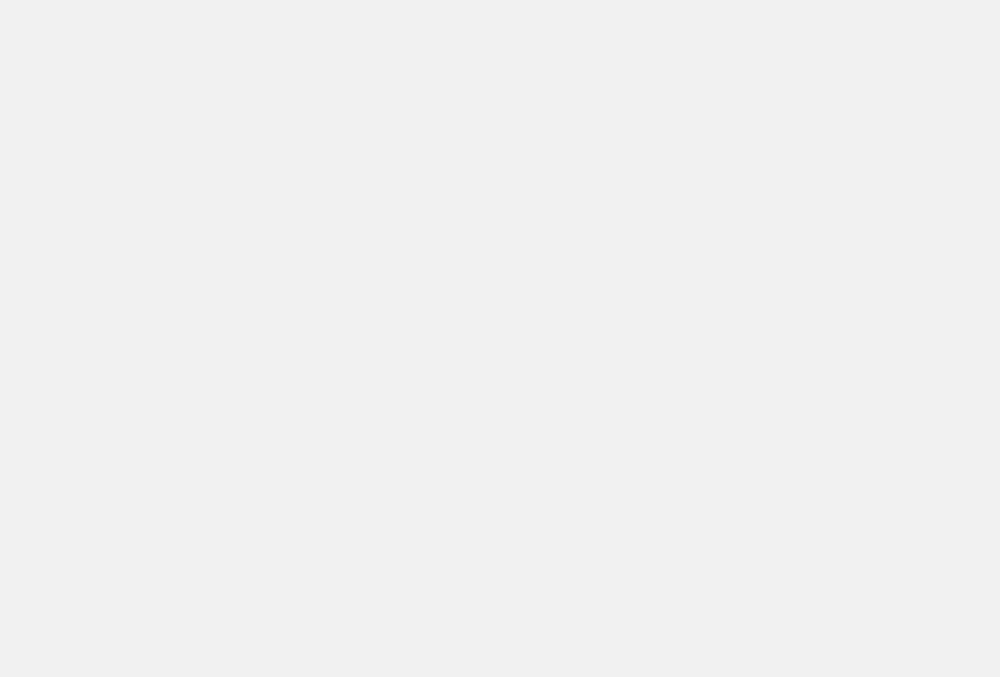


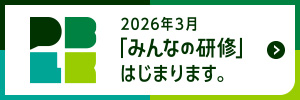




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
