アサーションとは?3つのタイプやアサーショントレーニングの具体例を解説

1.心理療法から生まれたアサーション
アサーションの発祥の地はアメリカです。1940年代後半に、人間は、自由で「活動的」な生き物であるが,多くの人は子ども時代に受けた躾(しつけ)や社会的規範などによって「抑制的」になってしまっていることから、本来の活動性を取り戻す意味でアサーション(自己主張)が必要であるという考え方が生まれました。
その後、「不安」という感情を軽くしたり、取り除いたりするための心理療法として、怒り感情の表出を含む主張行動として再び研究開発がなされました。
2.基本的人権としてのアサーション権
1960~70年代には、黒人や女性の権利を主張する人権運動が活発になる中、抑圧されてきた人々が適切に自己主張し、声をあげる方法としてさらに発展しました。
それは、アサーションのよりどころになっているのが、自己表現の権利という、生まれながらにして誰もが持っている基本的人権を認めることにあるからです。
つまり、アサーションは、誰もが持っているアサーションをする権利=「アサーション権」を受け入れるところから出発するのです。そして、このようなアサーション権は、人間関係の基礎となります。
3.現在のアサーション
私たちは、「頼まれごとを断るのは不親切だ」「自分の希望を言うことはひかえるべき」「落ち込んだり、腹が立っている時は、それを表現してはいけない」「部下は上司の意見に従うべきだ」など、社会の常識を優先して、自他の言動を制約することが多くあります。
そのような時は、私たちは性、役割、年齢、地位などによる固定化されたイメージで行動をしている可能性があります。
アサーションは、そのような自他を差別する基準を持たないようにすることから出発します。私たちは誰でも欲求を持って良いし、その欲求を大切にしてほしいと頼んでも良いのです。そんな時役に立つのが、「自分も相手も大切にした自己表現」である「アサーション」です。
4.アサーションから見た自己表現の3つのタイプ
アサーションでは、人の自己表現には次の3つタイプがあり、それらのすべてを各自が、相手や状況に合わせて行っていると言われています。アサーションを理解するために、先ず3つのタイプの自己表現を見ていきましょう。
(1)非主張的な自己表現
自分より相手のことを大切にしようとするため、自分の意見、気持ちを言わなかったり、相手にわかりにくい言い方をします。相手を優先しているとはいえ、実は相手に対して率直ではなく、自分にも不正直な言動です。
特徴として「人任せ」「自己否定的」「承認を求める」「服従的」などが挙げられます。相手と異なることを言うと嫌われるという考えや、面倒やもめごとなどを避けたいという思いが働いていたりします。
こういう自己表現は結果、弁解がましくなったり、相手に合わせたのに孤立して相手を恨むことなどにつながります。
(2)攻撃的な自己表現
相手より自分を優先に考えようとするため、自分の意見や考えははっきりと自己主張しますが、その際、大声で怒鳴ったり、暴力的に言うことを聞かせるだけでなく、相手の気持ちや言い分を無視したり言わせないようにして相手を思い通りに動かそうとします。
暴力的な言い方をせず、ほめあげて相手を自分の意のままに操る場合も攻撃的な自己表現に含まれます。
一見主体的に見えますが、相手が自分と違うことへの不安や逆らわれることへの恐れ、また、それらを認めることは負けることだと思っています。
特徴としては、「相手を支配しようとする」「他者否定」「責任転嫁」「操作的」などが挙げられます。こういう自己表現は、結果相互尊重の付き合いにはならず関係は長続きしません。
(3)アサーティブな自己表現
非主張的な自己表現と攻撃的な自己表現の中間で、自分の考えを正確かつ率直に言うことが出来ると同時に相手の立場や言い分もきちんと聞こうとする態度も含んでいます。
相手の言い分を聞き、反論や不賛成が返ってくることを恐れず、どのような状況にも率直に対応し自分の責任で次の言動をとろうと思っているので、言動はすがすがしく、相手にもさわやかな印象を与えることが出来ます。
特徴は、「自他尊重」「率直」「自己選択で決める」などが挙げられます。単に自分が言いたいことを率直に言う、あるいは、相手を傷付けないようにうまく表現するといった自己主張をするだけではなく、互いに譲り合いながら、納得感のある妥協点を探り合います。
又、異なる意見が出た時や結論を出せず迷っている時は、そういう自分を素直に認め、「わかりません」と態度を保留することもあります。
5.アサーションを身に付けるためのポイント
アサーションを身に付けるためには必要なポイントについて、見ていきましょう。
(1)自分の基本的な権利を自覚し、相手にも認める
当たり前のことですが、私たちには、自分のことは自分で決定する権利をもっています。 そして、この権利は、相手にもあるのだということをしっかり認めなくてはなりません。
人間関係は相手が子供や高齢者や家族であっても、対等・平等であることが基本です。
(2)相手のことをよく聴き、認める。
私たちは、コミュニケーションにおいて、「話す」ということに注力しがちですが、相互尊重に基づいたアサーションでは、相手の話を「聴く」ことも大切です。
勝手な推測や憶測で「あなたは〇〇〇だ」と決めつけることはせず、しっかりと会話を重ね確認することが必要です。相手を認め、信じてみることも相手を尊重した対話には欠かせません。
(3)「私は」を主語に自分を確かめる
私たちは、周りの人の言葉には敏感に反応しても、自分の「内なる声」に耳を傾けることは得意でない場合が多いものです。日ごろから自分の心や身体の声をじっくり聞き自分を注意深く観察してみましょう。
また、表現する場合にも相手を身構えさせる「あなたは」ではなく、「私は」を主語に話すようにすることで、スムースに言いたいことを伝えることが出来ます。
(4)葛藤を避けない
「一人ひとりが違っていて当たり前」ですから、コミュニケーションにおいて気持ちや考えが常に一致するとは限らず、葛藤が起こることもあります。
しかし、葛藤を避けるだけではよい結果を導き出すことはできません。自分自身を率直に開示する勇気と相手に自分を伝えたいという熱意をもって、積極的に踏み出すことが必要です。
(5)自分の常識や価値観を見直す
「〇〇するべき」「〇〇であるべき」など、自分の常識や価値観は時に、不合理な思い込みである場合があります。
他者との交流の中で、異なる常識や価値観に出会った際には、自己点検を行い自分の常識や価値観の修正を行っていく機会としましょう。
(6)自分の表現方法を見直す
表現には、適切な言葉による表現のほかに、表情・姿勢・動作・声・話し方などがあります。それらの点を振り返ってみることで、自分自身を伝える力を向上させることが出来ます。
又、話す際には、周囲の状況や相手の状態にも十分配慮し、誰かに注意する場合は人前を避けるなど、伝える際の状況判断も大切です。
それでは、具体的な活用方法についてお話しします。
6.アサーショントレーニングの方法
(1)DESC法とは
北米でアサーショントレーニングを行っているバイア―夫妻が開発した『DESC法(デスク法)』を紹介します。
DESC法は、英語のDescribe(描写する)、 Express(説明する)、 Specify(提案する)、Choose(選択する)の頭文字を取った言葉で、相手を不快にさせず自分の言いたいことを伝え、納得感を持たせる会話技法です。
<ステップ1>Describe(描写する)
自分が取り上げようとしている状況や問題、相手の言動などを描写する
●自分と相手が共有できる「事実」を具体的に表現する
●推測や自分の考えや気持ち、意見等は入れず客観的に表現する
<ステップ2>Express(説明する)
自分の考えや気持ち、意見等を表現する
●「私」を主語とした表現を行う
<ステップ3>Specify(提案する)
相手に望む行動、妥協案、解決策などの特定の提案をする
●決して、命令口調では行わない
●なるべく具体的で、現実的かつ小さな変化で済むようなことを考える
<ステップ4>Choose(選択する)
提案に対する肯定的・否定的結果を想像し、その結果に対する選択肢を示す
●相手にもアサーション権があることを認める
●否定的結果に対して、自分がどうするかも考えておく
(2)DESC法の具体例
例1)今日中に仕上げなければならない重要な仕事の作業中に、上司から「本日中に資料の作成を」と別の作業を指示された。
上司からの指示だからといって、毎回我慢しながら自分の考えや思いを伏せて対応していると心が疲れたり、関係性が悪くなることもあるでしょう。
だからといって「無理です」のような端的な表現をしますと、上司に本当の思いが理解されず、やる気がない、あるいは、ただの反抗に捉えられるなど誤解を与えてギクシャクすることもあります。
では、DESC法を使うとどのような表現が出来るでしょう。
【D】本日はプレゼンの資料作成の予定があり、終業時間までかかりそうです。
【E】このプレゼンを失敗するとみんなに迷惑が掛かってしまいますので、しっかり準備をしたいと思います。
【S】明朝でよろしければ、早く会社に来て作成します。
【C】
YES:では、明朝早く出社し、作業します。
NO:プレゼン資料作成を誰かにフォローしてもらえましたら、1時間はご依頼の作業ができます。
以上のように【D】では、主観を交えず事実を述べるところがポイントです。【E】では、自分の気持ちを述べたり、共感したりします。【S】では、打開策や提案を伝えます。【C】では提案を相手が受け入れなかった時に備え、選択肢を用意します。
例2)会議が長時間にわたってダラダラと続いている
会議がダラダラと続くのは、本当に非効率です。予定時間を超過している場合、DESC法を使って見ましょう。
【D】会議が始まって、そろそろ2時間が経過します。
【E】私は疲れて、集中力が切れてきました。
【S】このまま続けても、良い案が浮かびそうもないので、明日もう一度話し合うのは、どうでしょうか。
【C】
YES:また、明日頑張ります。
NO:では、休憩を少し入れて、終了時間を決めてみるのはどうでしょうか。
DESC法の重要なポイントは、自分の意見を押し付けるのではなく、お互いの妥協点を探しながら、解決策を提案することと、提案を相手が受け入れなかった時に備え、選択肢を用意することです。冷静に、落ち着いたトーンでWIN―WINを目指しましょう。
7.まとめ
アサーションという言葉を辞書で調べると、「主張」「断言」といった訳語が書かれており、自己主張をするあるいは、自分の意見をうまく通すといった偏った見方をされているケースがあります。
しかしアサーションがもたらすものは
●自分を大切にした納得のいく生き方
●対等で相互尊重の人間関係を築く素地
●自分の決断に責任を持ち、人のせいにしない生き方
●お互いの弱さや失敗、誤りを受け止められる寛容さ なのです。
コミュニケーションは、話す人と聞く人がいて成り立ちます。相手のことを尊重してしっかり話を聞きながら、自分の気持ちも大切にし、伝えたいことをしっかり言えるアサーティブな状態であることは、グローバル社会が進み、今後様々なものの見方や価値感を持つ人たちとの会話が求められる中で、ダイバーシティーを実現するための必須条件ともいえます。
自分自身の心身の健康のためにも、職場や組織の活性化のためにも是非、アサーションを身に付けましょう。
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 教育事業グループ
階層別・分野別・ビジネススキルの幅広いテーマを、さまざまな形でご提供しています。
来場型・Web型(ライブ配信/アーカイブ配信)で開催している「SMBCビジネスセミナー」、サブスクリプション方式による全社員の体系的な教育を可能とした定額制は「来場型の定額制クラブ」と「アーカイブ型の定額制Webセミナー」、カスタマイズ型の社員研修など、多数のラインナップをご用意しています。
https://www.smbcc-education.jp/





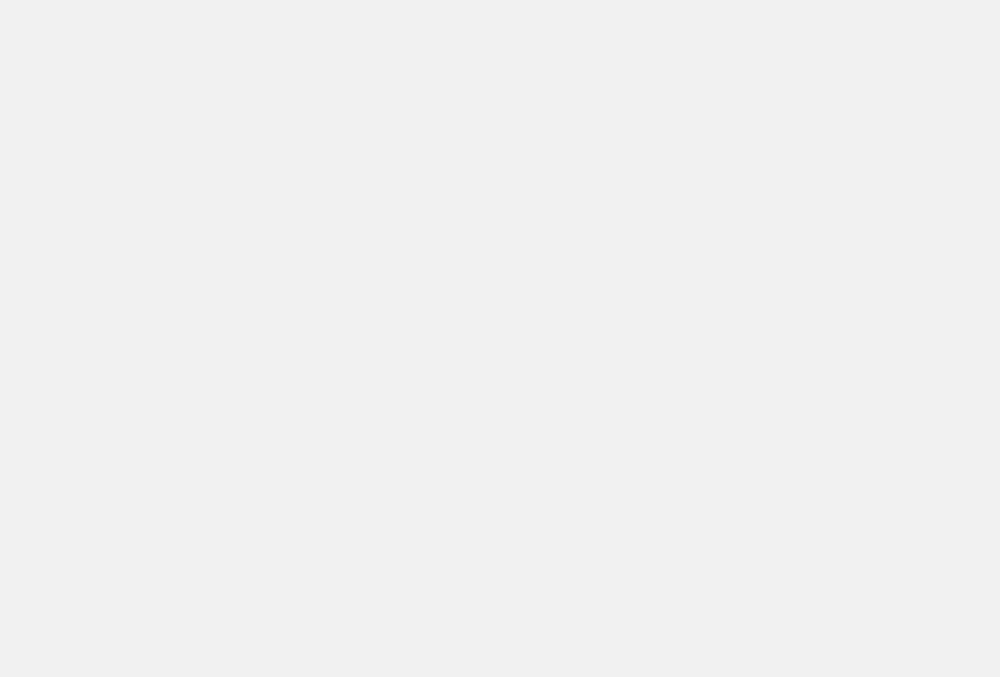

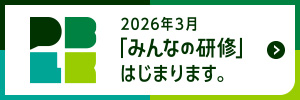




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
