Netpress 第2475号 多様化・複雑化するリスクに備える 企業不祥事から考えるコンプライアンス管理の実務

1.大きな企業不祥事では、根深い「企業風土」の問題、「聖域事業・聖域部門」、「非中核部門」、「グループ企業」といったリスク要因が指摘されています。
2.経営層には、流動するリスクへの「感度」と「柔軟性」、そして、リスクを受け止める「覚悟」を持つことが求められています。
1.企業を取り巻くリスクの現状
近年、企業を取り巻くリスクは多様化・複雑化し、ひとたび不祥事が起きれば企業の存続そのものが危うくなる時代となっています。
2023年上半期には上場企業による不適正会計が過去最多ペースで急増したと報じられているほか、品質・データ偽装事案、ハラスメント事案、情報漏えい、顧客情報の不正使用など、多岐にわたる不祥事が発生・発覚しています。
こうした不祥事は、非上場企業や中小企業にとっても決して他人事ではありません。
2.コンプライアンスの本質
現代において、こうした不祥事を防止し、企業と仲間(従業員)を守るためには、コンプライアンスの遵守が必要不可欠です。
こうした目的を果たすためのコンプライアンスは、単なる「法令遵守」に留まるものではなく、社会からの信頼や期待という「社会的要請」に応じること、換言すれば、企業が「言行一致」の姿勢を示し続けていくことを意味します。
3.不祥事例に見る企業に潜む不正リスク
大きな企業不祥事では、根深い「企業風土」の問題が共通して指摘されています。
具体的には、①上司の意向に逆らえない企業風土、②内向きの企業文化、③組織内の風通しの悪さ、④現場と経営の乖離、⑤コンプライアンス意識の不徹底、⑥目の前の不正に対する「他人事」、「無責任」、「無関心」の企業風土が挙げられます。
たとえば、東芝の不正会計事案では、上司の意向に逆らえない企業風土、三菱電機の品質不正事案では「言ったもん負け」という組織内の風通しを阻害する企業風土が要因とされています。
企業風土のほかには、組織内の「聖域事業・聖域部門」、「非中核部門」、「グループ企業」も不正のリスク要因となります。
こうした部門や組織はブラックボックス化しがちであり、その結果、十分な牽制やモニタリングが働かなくなってしまうためだと考えられます。
4.不正の未然防止・早期発見に必要な視点
不正の未然防止と早期発見を図っていくためには、何よりもまず、コンプライアンスの実践に対する経営トップの「言行一致」と「コミットメント」が不可欠です。経営トップには、ネガティブな情報(リスク情報)を歓迎し、そうした情報に正面から対応する姿勢を示すことが求められます。
次に、法令や規則に関する正しい「知識」も重要ですが、それだけでは、次々と発生する多種多様な問題や新たなリスクに適切に対処していくことは困難であり、役職員全員が、自分達の組織に求められる社会的要請に応えていくために何をすべきか、あるいは何をすべきではないのかという「意識」を高めることが不可欠です。
こうした意識を支えるのが、「企業風土」や「組織文化」であり、「ズルをしない」、「ウソをつかない(=正直に報告する)」、「目先の利益より長期の信頼を重視する」といった抽象的な規範(プリンシプル)を組織内に浸透させていくことが重要です。
さらに「VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代」においては、経営層自らがリスクに対する「感度」を上げるとともに、新たなリスクへの「変化対応力」、すなわちリスクへの「柔軟性」を高める必要があります。
リスクへの「感度」や「柔軟性」を上げていくためには、次のような姿勢が有効です。
① (社会動向や他社事例を参考に)「想像力」を働かせる
② 過去よりも将来(これからの社会動向)を見据えたリスク評価を行う
③ ネガティブ情報(聞きたくない情報)を歓迎し、積極的に対応する
④ 多様な意見・外部の目を尊重する
5.危機管理(非常時対応)の基本と留意点
(1) 危機管理の基本
危機管理の基本は、①損害の拡大防止(止血)、②事実調査、③原因究明、④再発防止の早期実行です。
特に人の生命身体や財産に深刻な被害が生じる事案では、何よりもまず、迅速な情報開示等による上記①の損害の拡大防止(止血)を図ることが最優先です。
この点、小林製薬の紅麹健康被害事案では、最初の腎疾患症例報告から対外公表・自主回収までに2か月以上を要したこと、つまり情報開示による損害の拡大防止(止血)の遅れが強い社会的批判を招くことになりました。
(2) 危機管理で求められる対応
危機に直面した組織に求められるのは、ステークホルダーに対する「説明責任」を果たすことであり、そのためには“事実”の“把握”が重要です。重大な危機管理案件においては、必要十分な調査体制を構築することで早期の事実把握を図る必要があります。
同時に、把握した事実の“見せ方”(危機管理広報)も重要であり、役職員には「Bad News First/Fast」の原則に基づく、正確かつ迅速な報告とタイムリーな情報開示が求められます。
6.終わりに ~会社と仲間を守るリスク管理を目指して~
会社と仲間を守るリスク管理を実践するためには、経営層が流動するリスクへの「感度」と「柔軟性」、そしてリスクを受け止める「覚悟」を持つことが必要不可欠です。
そのうえで、対応や判断が難しい事案においては、自分たちの対応について、
① 第三者に堂々と説明できるか(説明責任)
② 「言行一致」の姿勢を示していると言い切れるか
③ 今後も持続可能な対応といえるか
といった点について俯瞰的に検討することで、適切な意思決定につなげることができるものと考えます。
◎協力/日本実業出版社
日本実業出版社のウェブサイトはこちらhttps://www.njg.co.jp/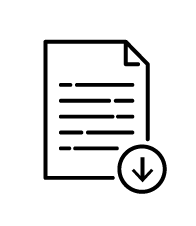
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




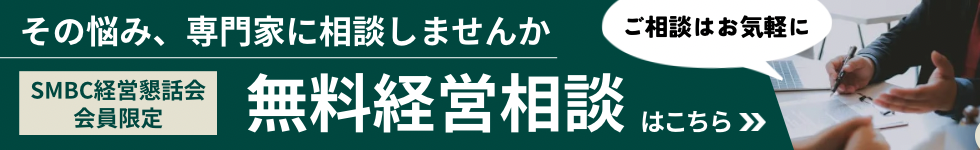
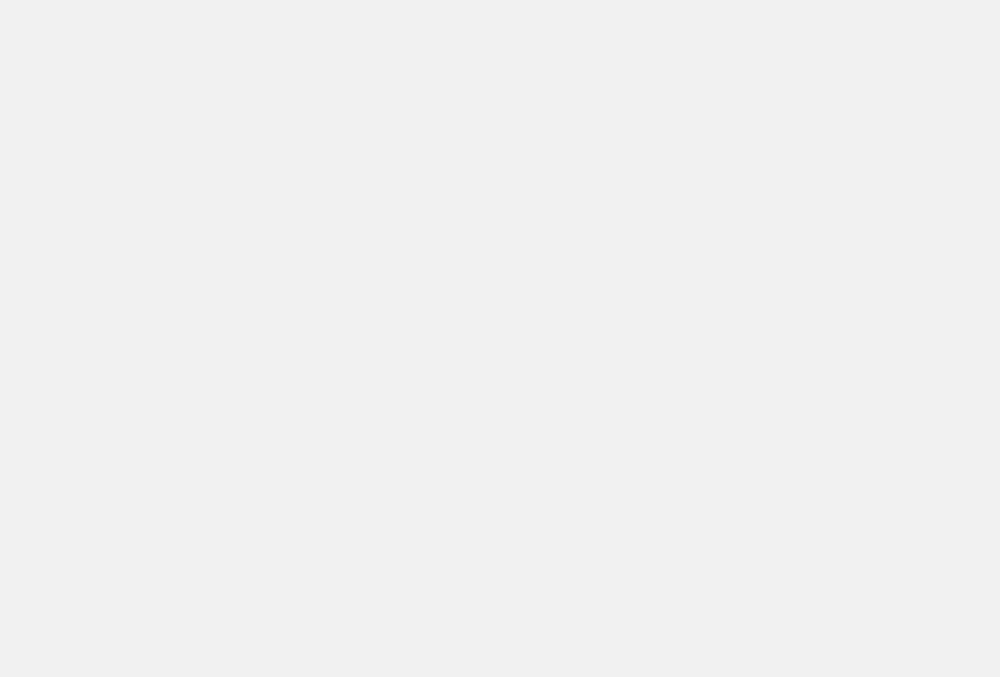

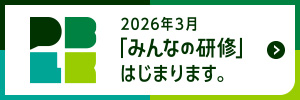




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
