Netpress 第2474号 【令和7年分】 所得金額の判定など年末調整に関する実務

1.令和7年12月の年末調整の際に「年収の壁」に関する制度改正の対応が必要です。
2.従来の基本的な実務に加え、制度改正を踏まえた知識を社員に伝える必要があります。
3.制度改正により、本人課税と配偶者控除や扶養控除の判定所得額が同額ではなくなりました。
令和7年分の年末調整においては、令和7年11月までの源泉徴収事務に変更が生じないようにされているため、令和7年12月の年末調整の際に改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表によって計算してきた源泉徴収税額との精算を行う必要があります。
また、従来の基本的な実務に加えて、「年収の壁」に関する制度改正を踏まえた知識を社員に正しく伝える必要があります。
ここでは所得税の改正を中心に解説しますが、「年収の壁」と一口に言っても所得税・住民税・社会保険など壁が何枚もあることが理解を妨げる要因となっています。
1.所得税における「年収の壁」
まず所得税における「年収の壁」ですが、重要なポイントがあります。それは本人課税の「ある・なし」と配偶者控除や扶養控除の対象と「なる・ならない」の判定所得金額が同額ではなくなったということです。
ここでは給与所得を例にとりますが、従前は給与所得控除55万円+基礎控除48万円の103万円が課税最低限だったものが、改正後の令和7年分からは給与所得控除65万円+基礎控除95万円の160万円となり、給与収入のみの人は160万円まで所得税が課税されないこととなりました。これは本人が所得税課税「される・されない」の「壁」になります。
ちょっと脱線しますが、社会保険については勤務先の会社規模が従業員51名以上であれば年収106万円以上で社会保険の加入義務があり、年収130万円以上になると会社規模等にかかわらず社会保険の加入義務があります。住民税は年収110万円を超えると課税されます。ただし社会保険の加入については他の要件がありますし、住民税も全自治体共通ではないので注意が必要です。
このように、本人が所得税・住民税を課税「される・されない」、社会保険料が「かかる・かからない」で4つの「壁」が存在しています。これに加えて、配偶者控除や扶養控除、特定親族特別控除を「受けられる・受けられない」の判定所得金額が異なります。
2.本人課税のある・なし
所得税の課税最低限は160万円となりますが、給与所得控除額も基礎控除額も所得の多寡に応じて減額されていきます。給与所得控除額と基礎控除額は、以下の表を参照してください。
【給与所得控除の額】(計算式)
| 給与等の収入金額 | 改正前 | 令和7年分以降 |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%−10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) | |
【基礎控除の額】
| 合計所得金額 | 改正前 | 令和7年・8年分 | 令和9年分〜 |
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 | |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | ||
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | ||
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | ||
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | ||
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | ||
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | ||
| 2,500万円超 | ― | ||
3.配偶者控除や扶養控除など
従来の扶養控除に加えて、特定親族特別控除が創設されました。
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族を特定親族と呼び、従来も特定扶養親族63万円の控除がありましたが、その特定親族の合計所得が58万円以下の場合に適用されます。
特定親族の合計所得金額が58万円を超えた場合は、下表のように所得に応じた特定親族特別控除額が適用されることとなりました。つまり、特定親族の給与収入が150万円以下なら63万円の控除が受けられるということになります。
【特定親族特別控除額】
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額)* | 特定親族特別控除額 |
| 58万円超 85万円以下(123万円超 150万円以下) | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下(150万円超 155万円以下) | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下(155万円超 160万円以下) | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) | 3万円 |
*特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
ちなみに、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件も48万円から58万円に10万円引き上げられました。
令和7年分の年末調整では、従来よりもさらに計算が複雑になっており、各種申告書の記載もより複雑になり、正確な所得記載が求められています。また社員に対する説明についても、本人課税の有無と扶養控除等の所得判定基準が同一ではなくなったことを丁寧に説明し、誤認識を防ぐことが求められます。
これらのことからも、従来よりも年末調整の準備期間を長くとり、社員の申告書作成、提出後の確認作業に十分な時間を取ることが大切です。
◎協力/日本実業出版社
日本実業出版社のウェブサイトはこちらhttps://www.njg.co.jp/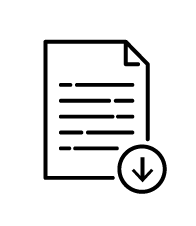
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




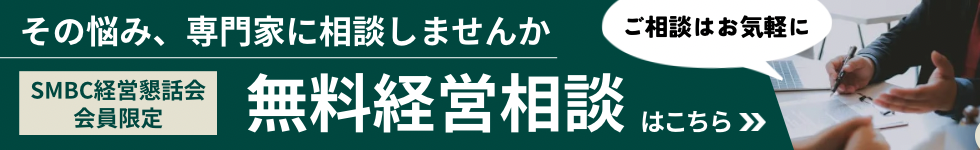

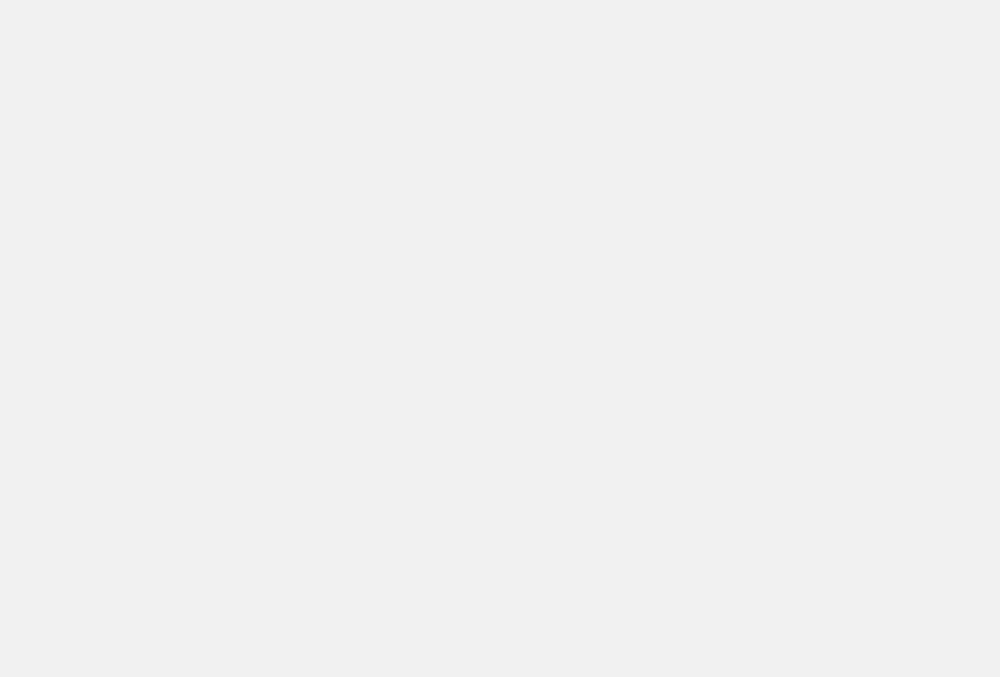

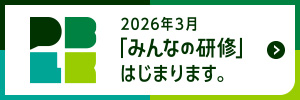




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
