Netpress 第2447号 制度改正等の動向を注視 法令からみた「副業・兼業」のポイント

1.労働時間外での副業・兼業は基本的に労働者の自由であり、これを制限するためには合理性が必要です。
2.企業は副業・兼業に伴う労務管理を適切に行う必要があり、そのための仕組みづくりが必須です。
3.あわせて、継続的に副業・兼業に関する制度改正等の動向を注視する必要があります。
副業・兼業については、2017年3月28日の働き方改革実現会議で決定された「働き方改革実行計画」を踏まえ、厚生労働省において2018年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の策定と「モデル就業規則」における副業・兼業規定の新設がなされ、その後も随時改定が行われています。
昨今では、副業・兼業を容認する企業や副業・兼業を希望する社員が増加傾向にあるとされ、また副業・兼業のマッチングサービスを提供する事業者も多く現れている状況です。
本記事は、副業・兼業に関し、主に企業側の実務における一助とすべく、基本的な整理を行うものです。
1.副業・兼業に関する基本的な考え方
労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされており(「副業・兼業の促進に関するガイドライン」2022年7月改訂版等を参照。以下、当該ガイドラインを「本ガイドライン」といいます)、労働者の私生活の尊重や職業選択の自由の要請が働くとされています。
そのため、副業・兼業を制限する内容の就業規則の合理性(労働契約法7条)については、厳格に判断されるものとされています。
2.モデル就業規則(届出制)
上記1の基本的な考え方を踏まえ、厚生労働省労働基準局監督課作成の「モデル就業規則」(2023年7月版)では、副業・兼業に関し、以下の規定を置き、労働者が副業・兼業できることを原則として明示したうえで(第1項)、例外的に過去の裁判例等を基に企業側による制限が許される場合を列挙し(第2項)、必要以上に労働者の副業・兼業を制限することがないようにすべきとし、(副業・兼業を認める場合)労務提供上の支障や企業秘密の漏洩、長時間労働の可能性の有無等を確認するため、労働者からの事前の届出により、労働者の副業・兼業の内容を把握すべき旨が記載されています。なお、本ガイドラインにも同旨の記載がされています。
(副業・兼業)
第70条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
3.許可制について
他方、企業側からみた場合、労働者が本業として雇用されている会社とは別の会社で就業することや、自ら事業を営むことにより、安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務、誠実義務等の点で問題が生じかねず、会社の利益を害するおそれが考えられます。そのため、就業規則において、会社の許可なく他に雇用され、また自ら事業を営むことを禁止し、この違反を懲戒事由とする(=許可制を採用している)企業は少なくないとされます。
裁判例では、「労働者が提供すべき労務の内容や企業秘密の機密性等について熟知する使用者が、労働者が行おうとする兼業によって(労働者の使用者に対する労務の提供が不能又は不完全になるような事態や、使用者の企業秘密が漏洩するなど経営秩序を乱す事態)が生じ得るか否かを判断することには合理性があるから、使用者がその合理的判断を行うために、労働者に事前に兼業の許可を申請させ、その内容を具体的に検討して使用者がその許否を判断するという許可制を就業規則で定めることも、許されるものと解するのが相当である」などとされており、許可性そのものを一律に否定するのではなく、個別具体的な事案ごとに就業規則の合理性を慎重に判断しています。
そのため、企業側においては、副業・兼業に関し、許可制を採用したうえで、過去の裁判例等を基に許否の判断を慎重に行うことが考えられます(過去の裁判例の集積として、モデル就業規則第70条2項①ないし④が参考となります)。
4. 副業・兼業を認める場合の対応
労働基準法第38条1項では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合を含むとされています(昭和23年5月14日付け基発第769号労働基準局長通達)。
そのため、労働者が企業に雇用される形で副業・兼業を行う場合、原則として労働時間を通算する必要が生じ、副業・兼業先の労働時間と自社の労働時間を合わせて、自社での労働が、法定外労働(1週間40時間または1日8時間を超える労働)に該当するときは、36協定の締結、届出、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。また、自社と副業・兼業先での法定外労働の時間と休日労働の時間を合わせて、単月100時間未満、複数月平均80時間以内とすることが必要です。
そこで、企業側は、副業・兼業に伴う労働者の労務管理を適切に行うため、労働者側から副業・兼業の有無・内容の確認を得るための仕組みを設けておくことが望ましいと考えます(本ガイドラインの解説では、労働者による副業・兼業に関する事前届出に加えて、管理モデルの導入や合意書の作成等が推奨されています)。
なお、2019年に施行された働き方改革関連法の附則等を踏まえ、働き方改革関連法の施行状況、関係制度の見直しの必要性等について調査・検討を行っていた労働基準関係法制研究会では、2024年12月の報告書(案)にて、割増賃金の計算のために本業先と副業・兼業先の労働時間を1日単位で細かく管理する必要があるため、運用が複雑で企業側に重い負担となっており、この煩雑が障壁となり、雇用型の副業・兼業の許可や受け入れが難しいとの指摘がある旨が報告されています。そして、同報告書(案)では、「こうした現状を踏まえ、労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ、割増賃金の支払いについては、通算を要しないよう、制度改正に取り組むことが考えられる」とし、「現行の労働基準法第38条の解釈変更ではなく、法制度の整備が求められることとなる」と提唱しています。これによれば、将来、割増賃金の支払いに関しては通算しない制度に変更される可能性があると言えます。
副業・兼業に関しては、今後も実情に応じた制度改正等が見込まれるため、企業においても、引き続き動向を注視する必要があると言えます。
日本実業出版社のウェブサイトはこちら https://www.njg.co.jp/
本記事を執筆した共栄法律事務所のウェブサイトはこちら
【SMBC経営懇話会会員限定】
SMBCコンサルティングの顧問弁護士による無料経営相談(大阪)のご案内
| 共栄法律事務所はSMBCコンサルティング株式会社の顧問弁護士です。 毎週火曜日と金曜日の10:00から17:00まで、SMBC経営懇話会会員向けの法律に関する無料経営相談を受けております。 無料経営相談の申込はこちら |
SMBC経営懇話会のサービスはこちらをご覧ください
SMBC経営懇話会のご案内
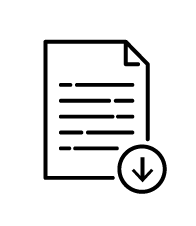
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




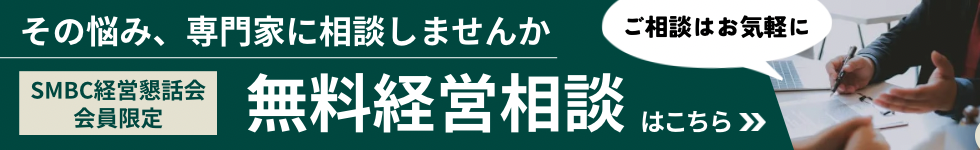

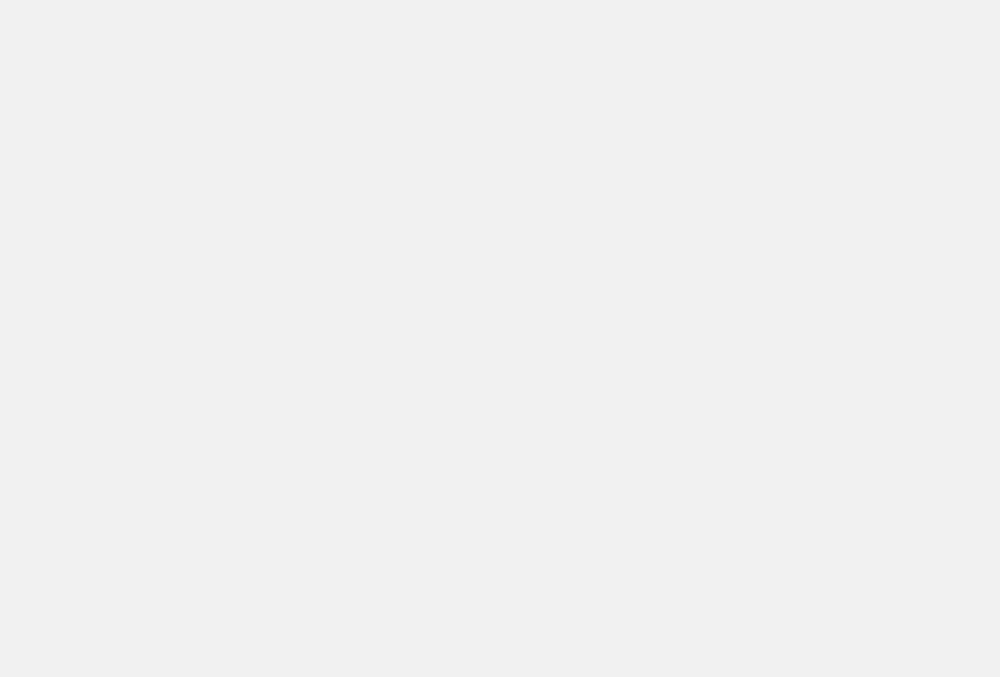

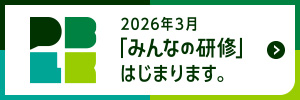




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方