Netpress 第2484号 人手不足解消のヒント 企業価値を高める戦力としての障害者雇用

1.障害者雇用を経営戦略の一部として活用し、成功している企業があります。
2.障害者社員の特性が活かせる業務へ配置することで、障害者社員は競争優位をもたらす戦力になります。
3.障害者雇用を成功させるためには、外部の専門家の協力を得て、ステップを踏んで進めることが大切です。
人材不足は今や中小企業にとって最大の経営課題の一つです。
2025年版「中小企業白書」によれば、実に6割を超える企業が「人が足りない」と回答しています。
図表 人材の過不足状況
2025年版中小企業白書 第2-1-41図より筆者作成
その一方で障害者雇用と聞くと、「義務だから仕方なく」「コストがかかる割に戦力にならない」と思われがちですが、障害のある人材を適材適所で活かすことで競争力を高めている中小企業が数多く存在します。
ここでは、3社の事例を通して「戦力としての障害者雇用」の可能性をお伝えします。
1.障害者雇用は“経営戦略”の一部
障害者雇用促進法により、企業には一定割合の障害者を雇う義務があります。
現在、法定雇用率は2.5%ですが2026年7月には2.7%へと引き上げられます。従業員数が37.5人以上の会社は、障害者を雇用する義務が発生します。
ここで重要なのは、経営資源として戦力化するという視点です。義務感ではなく経営戦略の一部として捉えることで、障害者雇用は人材不足解消にとどまらず、企業価値を高める投資へと変わります。
2.事例に学ぶ「戦力化」の実践
(1) М社(長野県茅野市・プラスチック成形)
プラスチック成形を手がけるМ社は、長野県の第1期SDGs認定企業です。入社間もない社員には年齢の近いメンターをつけ、相談しやすい体制を整備しています。
発達障害の特性の一つである高い集中力を持つ社員を金型設計部門に配置し、根気を要する金型設計を任せた結果、他社が断念した案件を受注できるようになりました。技術力を競争優位につなげています。
社長は「障害のある社員の特性こそ競争力の源泉」と語っています。
(2) R社(青森県青森市・産業廃棄物処理)
R社では、「働きづらさを持つ人が気兼ねなく働ける会社をつくる」という思いのもと、障害者を含む多様な人材を受け入れてきました。
身体障害のある社員は統括部長に昇格して会社を支える存在になり、聴覚障害のある社員もフォークリフト業務で活躍しています。
さらにB型事業所(*)と連携し、廃棄物の分別や「飛び出す絵本式」会社案内の制作などの新しい仕事の創出も行っています。青森県での最初の企業として、障害者雇用の優良事業所である「もにす認定」も受けました。
人材を制約ではなく可能性として捉える姿勢が、企業の持続的成長につながっています。
| *B型事業所: | 障害のある人が雇用契約を結ばずに通える「働く場」 です。一般企業のような賃金ではなく、作業内容に応じて「工賃」が支払われます。 |
(3) T社株式会社(東京都八王子市・電子部品製造)
T社が障害者雇用を始めたきっかけは「人手不足」でした。
午後2時半には退社するパート社員の業務の担い手として障害のある人材を採用し、実雇用率は9%超になっています。結果として余剰人員の発生もなく、設備の稼働率が向上しました。
採用は、福祉施設と連携して工場見学や実習を経たうえで行っています。また、月1回の面談で課題を共有し、離職リスクを防いでいます。
担当役員は「自社で抱え込まず、支援機関や専門家と連携することが重要」と語っています。
3.中小企業が得られる3つのメリット
これらの事例から、中小企業にとってのメリットは明確です。
① 人材不足の解消
シフト勤務の調整、検品や軽作業への配置などで生産効率や業務効率が向上します。
② 技術力・受注力の向上
障害者社員の特性が活かせる業務への配置により、製品の差別化や新規受注の獲得に繋がります。
③ 企業ブランドの向上
SDGsの推進や「もにす認定」の取得は、取引先や地域社会からの信頼強化につながり、障害のない社員の定着率向上にも寄与します。
4.実践の第一歩
企業の担当者から、「何から始めればよいかわからない」と質問されることがありますが、外部の専門家の協力を得てステップを踏んで進めることが大切です。
① 外部の専門家に相談する
自社ですべて対応しようと考えないで、ハローワークや就労移行支援事業所(*)などのノウハウや知識を活用した、採用・定着のサポートを依頼します。
② 担当業務を検討する
担当業務の決定のために、「自分以外の誰かに手伝ってほしい業務」という観点でリストアップします。紙の契約書のPDF化など、重要度は高いが緊急度の低い業務が向いています。
③ 小さく始める
職場実習の受け入れやトライアル雇用から取り組むことで、社風や業務と障害特性のミスマッチを抑えることが可能になります。
| *就労移行支援事業所: | 障害のある人が企業で働けるようにするためのサポートを行う障害福祉施設 |
5.義務からチャンスへ
障害者雇用は、「人手不足時代を勝ち抜く経営戦略」です。
多様な人材を受け入れることで、人員を確保し、新たな価値や競争力を生み出すことができます。
人を活かすことができる会社こそ、これからの時代に選ばれる会社です。
ぜひ「戦力としての障害者雇用」を、貴社の未来を切り拓く一手としてご検討ください。
◎協力/日本実業出版社
日本実業出版社のウェブサイトはこちらhttps://www.njg.co.jp/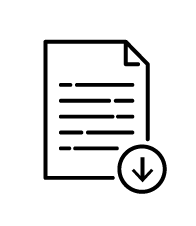
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




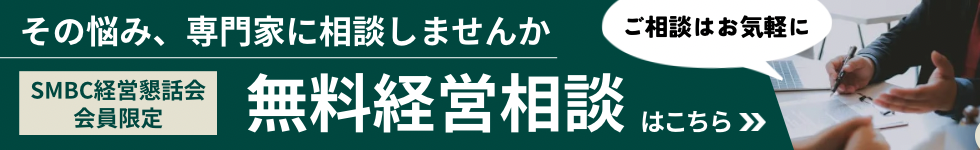

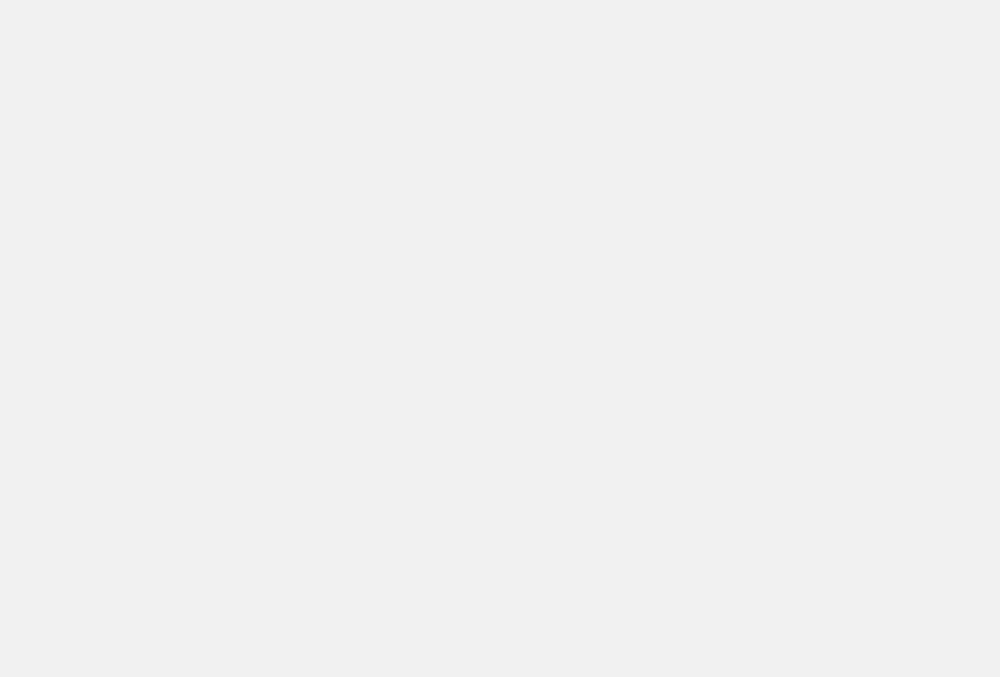
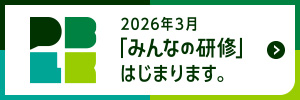




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
