Netpress 第2473号 「労災隠し」と疑われないために 労災事故発生時の基本的な対応と届出

1.労働災害などが発生した際に、労働基準監督署長への労働者死傷病報告の提出を怠ると「労災隠し」として問題になります。
2.労働者死傷病報告の提出に関して誤解しやすい点などを確認し、事業者がとるべき対応を解説します。
1.「労災隠し」とは
「労災隠し」とは、死亡または休業を伴う労働災害等(以下、「労災」)が発生したにもかかわらず、労働基準監督署長に報告をしないこと、または虚偽の報告をすることをいいます。
労働安全衛生法(以下、「安衛法」)100条では、安衛法の実効性を確保し労働災害の防止を図るために、労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官は事業者に対し、必要な事項の報告、出頭をさせることができる、とされています。この報告や出頭をさせることができる内容は、労働安全衛生規則(以下、「安衛則」)に定められています。
そのひとつとして安衛則97条では、「事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。」と規定されています。この報告を「労働者死傷病報告」といいます。
つまり、事業場等において労災により死亡または休業が発生した場合には、労働基準監督署長に労働者死傷病報告をしなければならないのです。
この報告について、安衛法120条には「報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または出頭しなかった者」等について、50万円以下の罰金に処する、と規定されています。安衛法120条に記載されている行為に該当し、違法かつ有責であった場合には犯罪となり、罰金が科せられ、前科となります。労災隠しは「犯罪」なのです。
2.労働者死傷病報告の提出のタイミング
労働者死傷病報告を提出するタイミングについては、安衛則97条に規定されています。提出するタイミングは、休業日数が4日に満たないかを基準に区分されます。
休業日数が4日以上である場合には、遅滞なく提出しなければなりません。4日に満たないときは、1年を1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月に分け、その期間における事実について、「それぞれの期間の最後の月の翌月末日まで」に労働基準監督署長に提出することとされています。
この「休業」の日数のカウントについては、被災日の初日は含まれないことに注意が必要です。たとえば、朝、出勤直後に負傷して早退したが、次の日には仕事のために出社した場合には、休業は0日のため、労働者死傷病報告を提出する必要はありません。
また、同様に労働者死傷病報告における4日の休業についても、被災日の初日は含まれないので、被災日の翌日から4日間の休業という意味になります。
一方、労災保険における休業補償給付の支給開始日は休業4日目とされていますが、この「休業」には被災日が含まれるため、労働者死傷病報告の場合と異なることに留意してください。
3. 労働者死傷病報告の報告方法
令和7年1月1日施行の改正により、労働者死傷病報告は電子申請が義務化されています。
電子申請については、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用することで、労働者死傷病報告を作成し、さらにe-Govを介して直接電子申請することが可能です。
この改正により、これまで自由記載であった部分について、コードから選択できるようになり、「災害発生状況及び原因」の欄も変更されています。
なお、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告でもよいとする経過措置が設けられています。
4. 労災隠しによる事業への影響
(1) 労働基準監督署等の対応
労災隠しに対しては、労働基準監督署による行政指導または捜査が行われます。
労災隠しは犯罪となりますが、他の労働法違反と同様に、ある日突然、労働基準監督官により捜査が始まり送検される場合より、まず行政指導が行われる場合が多いでしょう。
行政指導が行われた場合、速やかに行政指導に沿った改善を行う必要があります。行政指導が繰り返されても改善されない場合、送検される可能性が高まります。
行政指導は、労働基準監督官の指導に従えば対応可能な場合が多いと思われますが、専門家に相談するのであれば社会保険労務士がよいでしょう。
もし、捜査が開始された場合には、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
(2) 罰金刑以上の社会的影響
罰金刑が科されると、前科となるだけでなく、企業の信用を失うなどの社会的影響が伴います。たとえば、主要な取引先からの信頼を失い、取引が停止されるかもしれません。
また、入札の参加要件には、罰金刑が科されていないことが定められることが通常なので、入札参加資格を失う可能性があります。
(3) 建設業や運送業等の許認可が必要な業種は要注意
労災隠しが発覚した場合に、許認可が必要な業種については行政処分がなされることがあります。
行政より建設業の許可を得ている事業者が、労災隠しによる安衛法違反で罰金刑を科されたケースを検討してみましょう。
まず、安衛法違反は、建設業法8条の欠格事由には当たらないので、建設業法29条による欠格事由該当の建設業許可の取消しはありません。しかし、安衛法違反も対象となる建設業法28条の指示および営業の停止がなされる可能性はあります。なお、欠格事由に当たらないので、建設業許可の更新には影響しません。
次に、行政より運送業の許可を得ている事業者が、労災隠しで罰金刑を科された場合はどうでしょうか。
安衛法違反は貨物自動車運送事業法違反には当たらないので、運送業の許可には影響しません。しかし、運輸局と労働基準監督署は相互通報制度があるため、労働基準監督署が労災隠しのために調査を行った結果、付随して貨物自動車運送事業法違反となる事実が発覚すると、運輸局に通報されて行政処分等の対象となる可能性があります。
このように、許認可が必要な業種については、労災隠しが業務にどのような影響を及ぼすかについて十分に確認し、適切に対応しなければなりません。
◎協力/日本実業出版社
日本実業出版社のウェブサイトはこちらhttps://www.njg.co.jp/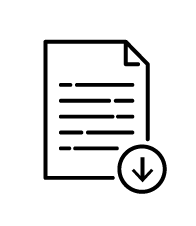
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




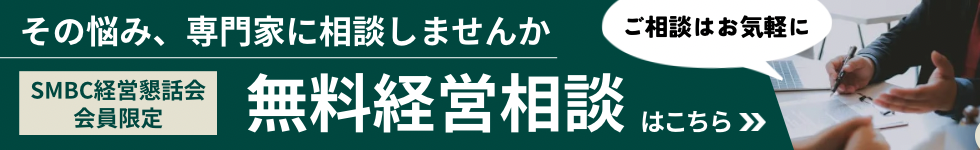

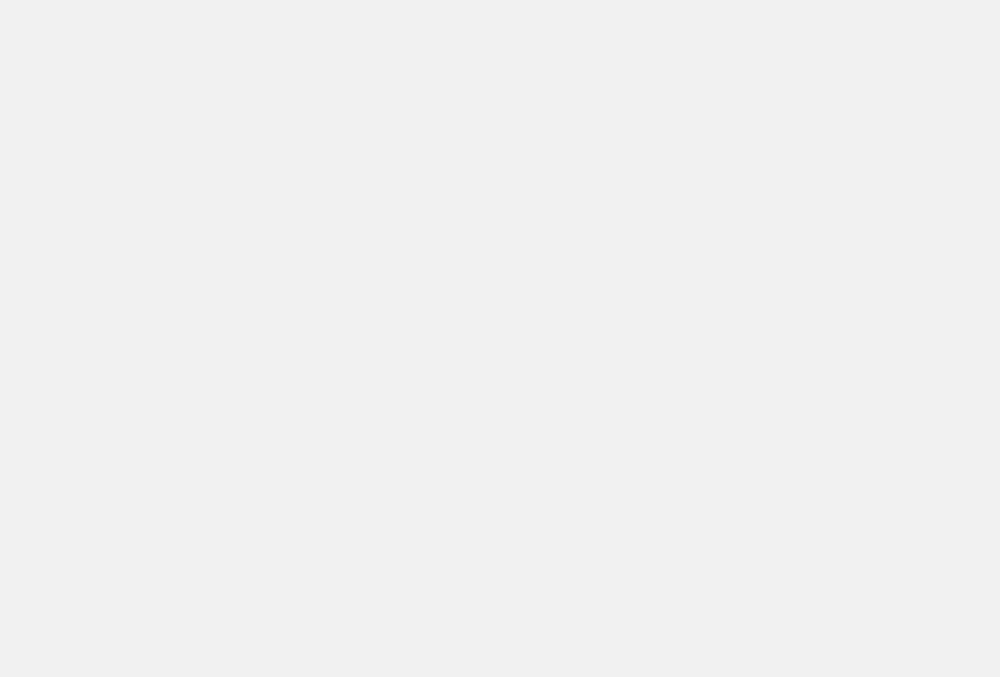

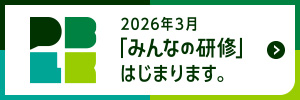




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
