Netpress 第2459号 制度や環境の整備など 不妊治療と仕事の両立のために会社ができること

1.働きながら不妊治療を受ける人は増加傾向にあり、治療と仕事の両立支援に取り組むことは企業にとってもメリットがあります。
2.両立支援には、当事者の「不妊治療をしていることを職場に知られたくない」という気持ちへの配慮や、個別のニーズに対する柔軟な対応が有効と考えられます。
女性の社会進出に伴う晩婚化・晩産化の影響で、不妊治療を受ける夫婦が増えており、働きながら不妊治療を受ける人が増加傾向にあります。
一方で、不妊治療を受けたことがある人のうち26.1%の人が不妊治療と仕事の両立ができずに離職したり、雇用形態を変えたり、不妊治療を中止したりしています(厚生労働省 2023年「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」より)。
不妊治療と仕事の両立が難しいという理由で貴重な人材を失うことは、会社にとって大きな損失となります。不妊治療を受けながら安心して働き続けられる職場づくりに取り組むことは、社員のキャリア形成やモチベーションの向上、優秀な人材の確保につながることが期待できます。
本稿が、「不妊治療と仕事の両立のために自社で何ができるか」を考えるきかっけとなれば幸いです。
1.不妊治療の現状
日本では、実際に不妊の検査や治療を受けたことがある(または現在受けている)夫婦の割合は22.7%で、これは夫婦全体の4.4組に1組となっています(国立社会保障・人口問題研究所 2021年「第16回出生動向基本調査」より)。
また、不妊は女性だけの問題と思われがちですが、男性に原因があることも少なくありません。不妊治療は、決して特別なことではなく、身近な問題であると認識する必要があります。
不妊治療の流れは、検査を行った後、タイミング法や人工授精からスタートし、体外受精や顕微授精へと進んでいくことが一般的です。
特に体外受精や顕微授精では、女性の月経周期に合わせて、ホルモン値や卵胞の状態を確認しながら治療の日程が決定されるため、突発的で頻繁な通院が必要となります。
不妊治療と仕事の両立の難しさは、こういった時間的な問題が大きく影響しています。
2.不妊治療と仕事の両立支援の事例
不妊治療と仕事の両立支援が重要課題の一つであるという認識は広がりつつあります。
しかしながら、会社には伝えずに不妊治療を行っている人も多いため、実態を把握しづらく、自社の問題ではないと考えている会社も多いのではないでしょうか。
アンケート調査によると、不妊治療を行っている社員が受けられる支援制度がない企業が73.5%にも上っています(厚生労働省 2023年「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」より)。
では、両立支援を行っている会社では、具体的にどのような取り組みが行われているのでしょうか。
大きく分けると、①休職制度、②休暇制度、③柔軟な働き方に関する制度が挙げられます。
| ① 休職制度 | 不妊治療を目的とした休職 |
| ② 休暇制度 | 不妊治療を目的とした休暇、不妊治療を多目的休暇(家族休暇、治療休暇、積立年休)の取得要件の一つとする など |
| ③ 柔軟な働き方に関する制度 | 時間単位の年次有給休暇、フレックスタイム制、テレワーク、短時間勤務 など |
不妊治療と仕事の両立支援は、育児や介護のように法律に基づいて制度を導入するわけではありません。
また、仕事内容、夫婦の方針、受けている治療の段階、体調、通院している病院の場所などにより、社員の制度に対するニーズもさまざまです。
そのため、制度化せずに相談があれば個別に対応している会社もあります。
3.両立支援導入にあたってのポイント
厚生労働省の「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」によると、両立支援の取り組みを行うステップは、次の通りとされています。
| 【ステップ1】 取組方針の明確化、取組体制の整備 |
| 【ステップ2】 社員の不妊治療と仕事との両立に関する実態把握 |
| 【ステップ3】 制度設計・取組の決定 |
| 【ステップ4】 運用 |
| 【ステップ5】 取組実績の確認、見直し |
不妊治療と仕事の両立支援の難しさの一つに、「不妊治療をしていることを職場に知られたくない」という気持ちへの配慮が挙げられます。
利用しやすい制度とするためのポイントとして、たとえば休暇であれば、不妊治療の支援であることを前面に出さず「ファミリー休暇」「ライフプラン休暇」等の名称で、他の目的(育児、介護、闘病など)に不妊治療を加える方法があります。人事担当者など一部の人にだけ休暇の取得目的を伝えれば済むような運用にしておけば、休暇取得へのハードルを下げることができます。
また、不妊治療をしていることを職場へ伝えることを躊躇する原因として、不妊治療に関する理解のなさ(偏見やハラスメントの懸念)、個人的な事情で仕事を休むことへの気苦労などがあります。不妊治療に対する理解促進のための啓発を行ったり、「お互いさま」と助け合える職場風土の醸成をあわせて進めたりすることもポイントとなります。
なお、不妊治療と仕事の両立支援として特別に制度を設けることが難しくても、年次有給休暇など現状ある制度について、利用しやすい環境づくりをすることだけでも支援につながります。また、社員向けの相談窓口を設けるといったことも、両立支援の第一歩になるでしょう。
不妊治療と仕事の両立に関して相談があれば柔軟に対応できるよう、自社の現状の制度の中で活用できそうなものを整理しておくことも大切です。
◎協力/日本実業出版社
日本実業出版社のウェブサイトはこちらhttps://www.njg.co.jp/本記事を執筆した社会保険労務士法人トムズコンサルタントのウェブサイトはこちら
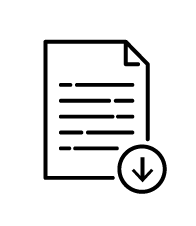
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
【SMBC経営懇話会会員限定】
SMBCコンサルティングの顧問社労士による無料経営相談(東京)のご案内
| 社会保険労務士法人トムズコンサルタントはSMBCコンサルティング株式会社の顧問社会保険労務士です。毎週水曜日の10:00から17:00までと金曜日の13:00から17:00まで、SMBC経営懇話会会員向けの労務に関する無料経営相談を受けております。 無料経営相談の申込はこちら |
SMBC経営懇話会のサービスはこちらをご覧ください
SMBC経営懇話会のご案内
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




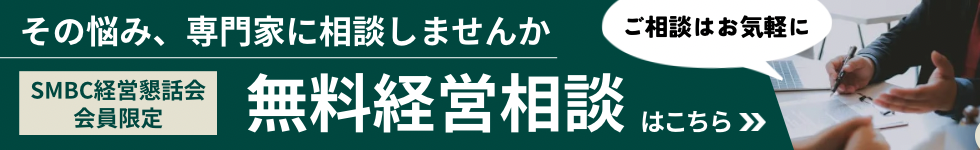

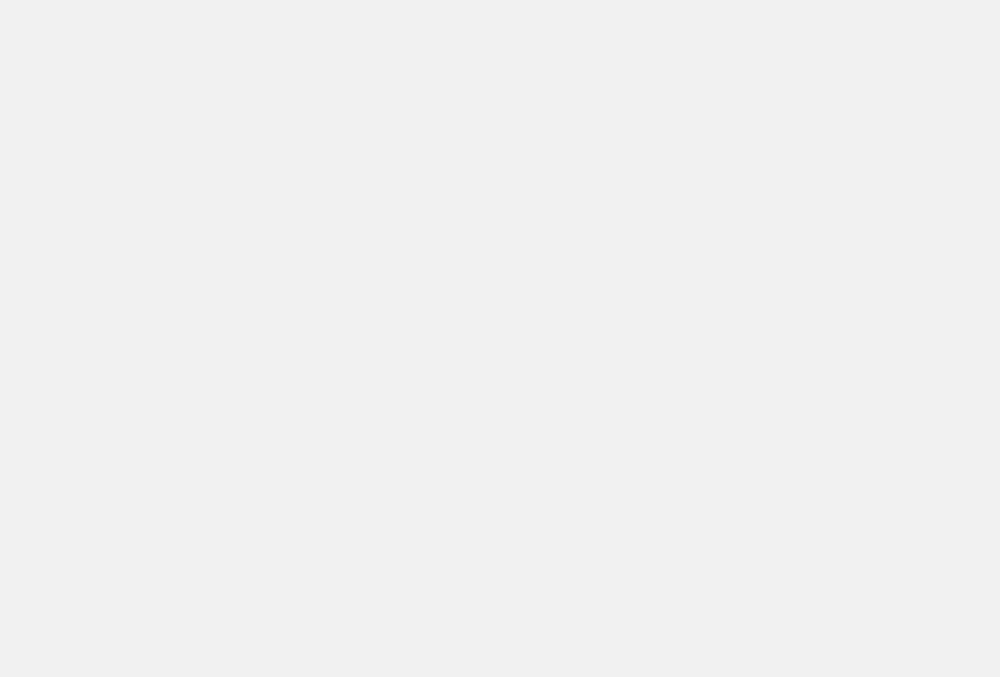


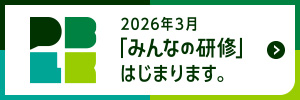




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
