Netpress 第2470号 コストをかけずに効果を高める! 社員研修を成功させる6つのポイント
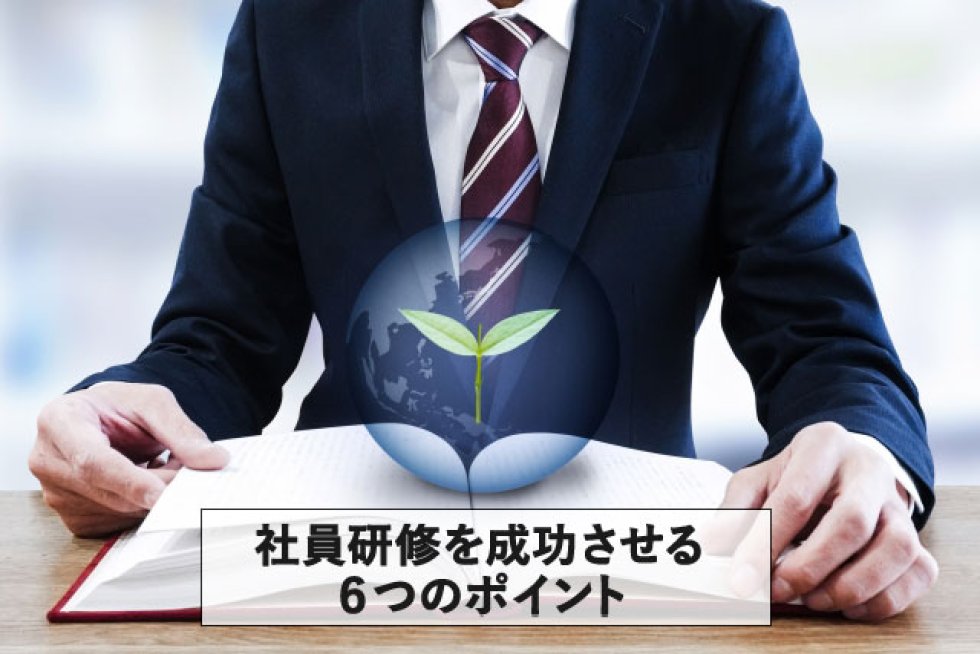
1.変化の激しいビジネス環境において、社員が新しく得たスキルや知識は企業の生産性向上に寄与します。
2.ここでは、社員研修の種類と効用を確認したうえで、研修を成功させるための6つのポイントを紹介します。
1.社員研修の種類と効用
社員研修は、大きく分けて「階層別研修」「スキル別研修」「法令関連研修」の3つに分類されます。
(1) 階層別研修
新入社員研修、新任管理職研修など、社員の職位や経験に応じて実施する研修です。各階層に求められる役割や責任を理解し、必要なスキルを習得することで、円滑な組織運営を実現します。
(2) スキル別研修
業務遂行力、コミュニケーション力、問題解決力など、特定のスキル向上を目的とする研修です。
近年では、外国人材の定着や女性活躍推進など、時代のニーズに応じた新しいテーマの研修も増えています。
(3) 法令関連研修
雇入れ時の安全衛生教育、コンプライアンス研修など、社会人として必須の各法令に関する研修です。労働安全衛生法では、企業が労働者に対して所定の安全衛生教育を行うことなどを義務付けています。
2.研修を成功に導く6つのポイント
以下に紹介する6つのポイントを押さえることで、コストを抑えつつ大きな効果を得る研修を行うことが期待できます。
| ●ポイント1――研修を実施する目的の明確化 |
研修を成功させるためには、まずその目的を明確に設定することが重要です。目的が不明確なまま研修を実施すると、社員は何を学ぶべきかわからず、研修の効果が薄れてしまいます。
新入社員、中堅社員、管理職など階層によって求められるスキルや知識は異なるので、どの社員にどのようなスキルや知識を身に付けさせたいのかを具体的に定め、かつ、社員に理解させることが重要です。
研修の冒頭に、経営トップから研修目的や参加者に期待していることを直接語ってもらうと効果が高まります。
また、社員のニーズを把握することも大切です。研修内容が社員の関心や業務に直接関わりのあるものでなければ、参加意欲が低くなり、効果が得られにくいからです。社員が抱える課題や必要だと考えているスキルを事前にヒアリングし、それに基づいて目的を設定しましょう。
そのうえで、各階層に応じた研修プログラムを設計し、必要なスキルを段階的に学べるようにします。社員の意見を研修プログラムに反映させることで、より実践的で効果的な研修となります。
| ●ポイント2――社内リソースの効果的な活用 |
社内の人材を活用し、社員が講師を務めることで、講師と参加者双方の成長機会となります。
特定の分野において優れた知識や経験を持つ社員を講師として、専門知識を共有する社内研修を定期的に開催することで、組織全体の知識レベルの向上を図ることもできます。
先輩である管理職社員が管理職研修の講師を務め、実際の課題をケーススタディとして取り上げ、課題の解決方法を共有するケースもあります。そういった研修を通じて、何らかの壁にぶつかったときに相談したり、助け合ったりできる職場環境を整えることも可能です。
社内リソースの活用は、外部講師に比べて低コストで、社員同士のコミュニケーションを深める効果もあります。
| ●ポイント3――オンライン研修の戦略的な活用 |
コロナ禍を機に普及したオンライン研修は、時間と場所の制約を解消し、集合研修と比べて交通費や移動時間などの削減も可能です。
ただし、一方的な講義形式では集中力が続きにくいため、チャット機能を活用した質疑応答など、参加型の要素を取り入れると効果的です。
研修を録画すれば、繰り返し視聴できるため、長期的な学習効果も期待できるでしょう。
また、eラーニングを活用すれば、スキマ時間を利用するなど社員が自分のペースで学習できます。
| ●ポイント4――研修とOJTとの効果的な連携 |
OJTで、研修で学んだスキルを実際の業務で活用する機会を設け、業務での実践を通じて定着を図ります。
実際の業務を通じて、先輩社員や管理職社員から直接フィードバックを受けることにより、理論と実践が結び付きやすく、社員の着実なスキル向上につながります。
| ●ポイント5――効果測定とフォローアップの実施 |
効果測定として、参加者に対して研修の満足度や学びの実感などのアンケート調査を行い、その結果を次回以降の研修に活かします。
また、参加者が研修で学んだ内容を持続的に活用できるように、フォローアップの実施も有効です。研修後に定期的に進捗を確認し、学んだことを実践できているか、行動変容を促しているかをチェックしたり、研修の参加者同士で、実践に役立つ情報を交換する場を設けたりすることも効果があります。
| ●ポイント6――社員の主体性を引き出す工夫 |
研修は一方通行の講義形式ではなく、双方向のコミュニケーションを重視することが大切です。
社員が実際の業務で直面する課題を取り入れたロールプレイやグループワークなどを行うことにより、自分事として捉えることで理解が深まります。
また、参加者同士で意見を交換し合うことで異なる視点を学ぶことができ、グループで解決策を考えることで、実践的な学びが得られます。積極的に参加できる環境を整えることで、能動的な参加を促し、学習効果が高まります。
研修を一過性のイベントで終わらせないためには、日常的な学習機会の創出が重要です。学びを通じて自己成長を実感し、職場での貢献を感じることで、仕事に対する満足感が高まるでしょう。
学びを楽しむ姿勢が、仕事のモチベーションを維持する助けにもなります。資格取得支援制度の導入や部門横断的な学習コミュニティの形成など、自発的な学びを促進する環境づくりも効果的でしょう。社員が自ら学び続ける組織風土をつくることが大切です。
◎協力/日本実業出版社
日本実業出版社のウェブサイトはこちらhttps://www.njg.co.jp/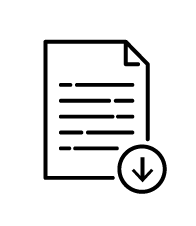
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
SMBCコンサルティングによる社員研修(講師派遣)
| 社員研修(講師派遣) | 実績豊富な講師ネットワークにより、企業様のご要望にお応えする研修支援サービス。 公開講座・定額制などを組み合わせた最適なプログラムをご提案します。 |
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




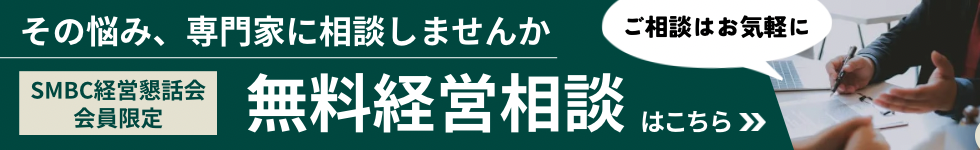

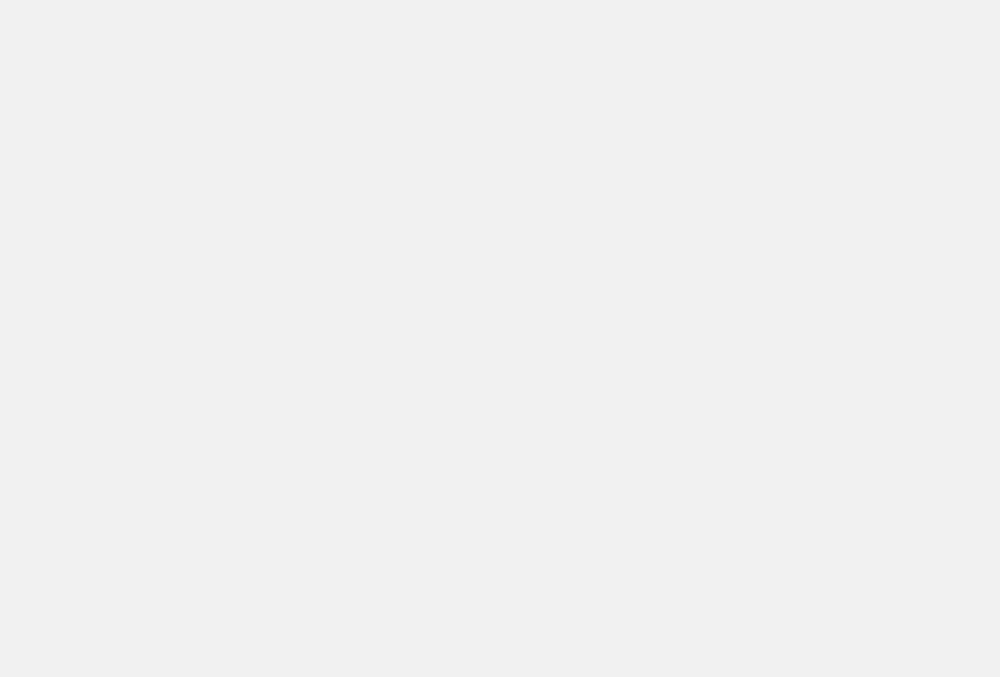





 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
