Netpress 第2457号 採用前に見抜く! 採ってはいけない人の特徴と見分け方

1.ひとたび“問題社員”を採用してしまうと、その後の対応には相当の労力やストレスがかかります。
2.採用段階できちんと見抜いてスクリーニングするために、採ってはいけない人を見抜くポイントを解説します。
1.採ってはいけない人の3タイプ
まず、採ってはいけない人は、次の3タイプに分けられます。
① ハラスメントタイプ
② 勤務態度不良タイプ
③ コミュニティ・クラッシャータイプ
①の「ハラスメントタイプ」は、周囲にパワハラやセクハラなどのハラスメントを行ってしまう人のことです。
近年、とくにパワハラが問題化しています。厳しい指導とパワハラの境界線が難しいこともあることから、無意識にハラスメントを繰り返してしまうタイプの人もいるのが現状です。
②の「勤務態度不良タイプ」というのは、具体的には「遅刻や欠勤が多い」「指示やルールに従わない」「周囲との協調性が著しく低い(独善的、チームの和を乱す)」「やる気がまったく見られない」「改善の意思がない」といった人です。
そして③の「コミュニティ・クラッシャータイプ」は、聞き慣れないかもしれませんが、近年とくに問題視されています。このタイプは、社内で影響力のある人には媚び、立場が弱い人には高圧的な態度を取ります。さらに、「リーダーや主要メンバーの陰口を言う」「平気で嘘をつく」といった問題行動も取ります。その結果として、コミュニティ内の関係性を悪化させ、そこに所属する人たちの間にあった絆が壊れ、徐々にコミュニティ自体が崩壊していきます。
これら3つのタイプの人は、人事担当者や経営者、現場マネジャーなどを日頃から悩ませている存在です。こうした人を採用してしまうと、その後の対応に相当の労力やストレスがかかりますので、採用段階できちんと見抜いて、スクリーニングしておきたいところです。
2.採用時点で見抜く方法
採ってはいけない人を採用時点で見極める方法として、次の3つの手法が挙げられます。
① 「面接」で、前職までの経験・行動を具体的行動レベルにまでフォーカスして確認する
② 「面接」で見抜けなかった場合の保険として「適性検査」を活用する
③ 「面接」と「適性検査」で不安が残る場合は「リファレンスチェック」を行う
これらの選考手法の特徴を踏まえたうえで、最優先で行うべきは、面接官の面接力の向上です。
面接は3つの手法のなかで最もポピュラーな選考手法であり、ほとんどの会社で導入されているのではないでしょうか。だからこそ、まずはいつも行っている面接のやり方から変えていきましょう。
まず、面接では候補者がこれまでの職場でどういった経験をし、行動を取ってきたのか、できるだけ詳細に深掘りします。たとえば、「これまでに、個人で完結するタスクではなく、チームプレーを活かして課題解決に取り組んだ象徴的な経験があれば教えてください」といった周囲への向き合い方がわかる経験を指定して質問を投げかけていきます。
さらに、続けて以下の質問で深掘りをするとより効果的です。
| ● | 会話の質 | ・ | メンバー(部下を含む)と、仕事に関するコミュニケーションをどのように取っていましたか? |
| ● | 利他的行動の有無 | ・ | 困っているメンバーや遅れが生じているメンバーがいたときは、どのように行動しましたか? |
| ・ | 自分の役割以外のことのために、自主的に取った行動などはありますか? | ||
| ● | 対人コンフリクト(衝突)との向き合い方 | ・ | チームで仕事を行う際、進め方や決定事項で他のメンバーと意見が衝突したり、考えが大きく違ったりしたとき、どのように対応してきましたか? |
これらの質問によって、マネジャー級の候補者であれば、過去に部下に対してどのように指示を出していたのか、本人が気づいていないハラスメントと捉えられるようなコミュニケーションがなかったかなどがわかります。
また、無意識にチームの和を乱す行動をしていなかったか、チームで決めたルールやポリシーにきちんと従っていたかなどもわかるため、「勤務態度不良タイプ」を見抜くこともできるでしょう。
ちなみに、「コミュニティ・クラッシャータイプ」が語る成果や実績などは、「できる人のそばで見ていただけ」「部下にやらせただけ」といった、本人がただ乗り(フリーライディング)しているだけのケースが非常に多く見られます。
そこで、「他の誰でもない自分自身が考えたことや取った行動」を聞いてみましょう。さらに、面接で見抜けなかった場合のために「適性検査」の活用もおすすめします。職場を壊すような、採ってはいけない人を見抜くことに特化した適性検査も多く存在します。面接と適性検査の結果を総合的に判断することで、精度の高い評価が可能となります。
そして、「面接でも適性検査でも問題はなかったが、それでも怪しい感じがする」といった候補者については、過去の上司・同僚・部下などの第三者に問い合わせる「リファレンスチェック」を行うことも検討しましょう。
リファレンスチェックは、コンプライアンスに厳しい外資系企業や金融機関などが行うイメージがあるかもしれませんが、最近は比較的手軽に実施できる外部サービス(株式会社ROXXが提供する『back check』など)もあります。
3.それでも採ってしまった場合の留意点
日本の雇用法制において、一度採用した社員を解雇するのは非常に難しいのが現状です。横領などわかりやすい犯罪行為でなければ懲戒解雇の処分も簡単には下せません。
ただし、たとえば降格などの処分については、事実としての明確な証拠があり、再三の注意・勧告を行ったうえであれば、訴訟などを起こされても合理的であると判断されるケースも多くあります。そのため、日頃からきちんと記録をつけておくことが重要です。個々の社員について、日常の気になる行動や発言などはノートに書き留めておきましょう。
決して、印象だけで評価したり、第三者の声を聞いたりしただけで判断してはいけません。ハラスメントであっても、勤務態度不良であっても、周囲の人間関係を壊すコミュニティ・クラッシャー行為であっても、「いつ、どんな場面で、どんな発言・行動を取り、それによって周囲や相手にどんな影響を与えたか」という具体的事実を集めたうえで、行動改善を要望したり、最終的な処分を下したりしなければなりません。
また、人事担当者としては、問題行動が起こりやすい職場体質(周囲が不正やハラスメントなどを容認したり、見て見ぬふりをしたりする組織文化など)がないかといった点も、フラットに考える必要があります。
問題行動が起こりやすい職場体質がある場合には、抜本的な改善を図るために、全社的な社内ルールの見直し、社員の行動規範の設定と浸透施策などを行っていく必要があるでしょう。
◎協力/日本実業出版社
日本実業出版社のウェブサイトはこちらhttps://www.njg.co.jp/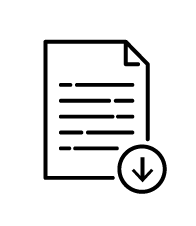
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




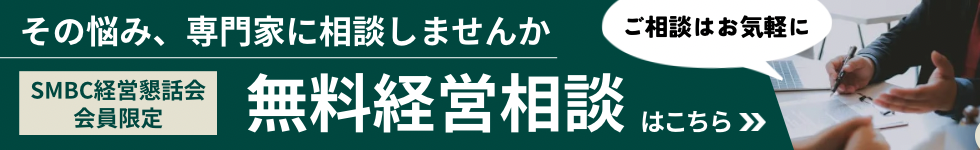

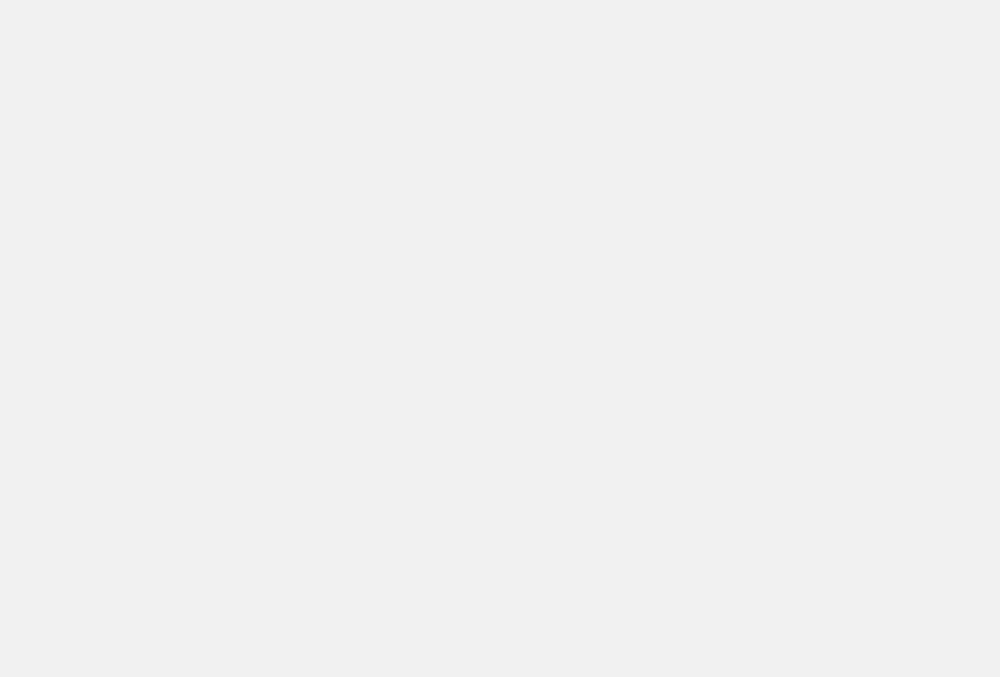


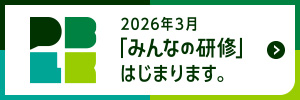




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
