Netpress 第2418号 生産性アップ! ストレス対処法 「コーピング」のススメ

1.ストレスと上手に付き合うためにまず大事なのは、自分のストレスのサインに気付くことです。
2.そのうえで、ストレスに対処する手法として効果的な「コーピング」を実践・導入するポイントを紹介します。
1.「コーピング」とは
私たちのストレスは、「ストレスの原因となる刺激」である「ストレッサー」と、ストレッサーを経験した結果として生じる「心身の変化」である「ストレス反応」の2つの要素に分けられます。
ストレスに対して、科学的に効果が認められている対処スキルの1つに「コーピング」という考え方があります。
当社(洗足ストレスコーピング・サポートオフィス)では、「コーピング」を「自分のストレス(ストレッサー、ストレス反応)に対して行う意図的な対処」と定義付けています。
ストレスへの対処というと、気分転換やストレス解消をイメージするかもしれません。これらもコーピングの1つですが、コーピングとは、もっと広い概念のことをいいます。
コーピングには、主にストレッサーに対処する「問題焦点型」と、ストレス反応に対処する「情動焦点型」の2つがあります。さらに、その手法から、具体的に行動することで解決を図る「行動型」のコーピングと、解決策について考える、考え方の幅を広げるといった、頭の中で行う「認知型」のコーピングに分類することができます。
(1) 問題焦点型コーピング
「問題焦点型コーピング」は、ストレッサーとなる状況の解決を図る方法です。
たとえば、業務マニュアルの作成が思うように進まないとき、「上司に相談して助言をもらう」(行動型)、「資料を見直し、課題や改善点を考える」(認知型)などが挙げられます。
(2) 情動焦点型コーピング
「情動焦点型コーピング」は、ストレスを受けた感情のケアや立て直しを図る方法です。
たとえば、「旅行でリフレッシュする」(行動型)、「現状のよい面を考えてみる」(認知型)などが挙げられます
2.コーピングを使いこなす
(1) 状況に応じたコーピング
ストレスに強い人は、複数のコーピングを持っており、自身の状況に応じてコーピングを使い分けています。
たとえば、読書をする、好きな映画を観るといったコーピングは、心がザワついて落ち着かないときには難しいこともあります。このようなときは、無心になって走る、ヨガを行うといった別のコーピングを試してみるのがおススメです。
また、仕事が忙しくて行動型コーピングのための時間が取れないときは、「何とかなる」と仕事に対する考え方の幅を広げるのも1つの方法です。
(2) コーピングを組み合わせる
複数のコーピングを組み合わせて行い、ストレッサーとストレス反応の両方に対処していくことも重要です。
たとえば、仕事のストレスに対して「同僚にサポートを求める」といった問題焦点型コーピングを行うことは、根本原因を解決するために有効ですが、その効果はすぐに現れてくれないこともあります。
そこで、「家族や友人に愚痴を聞いてもらう」「旅行でリフレッシュする」といったストレス反応に対処する情動焦点型のコーピングを組み合わせて行えば、根本原因が解決されるまでのストレスに対処することができます。
(3) 「MYコーピングリスト」を作成する
筆者が、企業研修やカウンセリングで実際に使用している「MYコーピングリスト」の作成方法を解説します。
◎STEP1:ふだん自分が使っているコーピングを書き出す
まずは、「散歩をする」「音楽を聴く」「温かいお茶を飲む」など、自分が日頃ストレスを感じたときに行っている行動を書き出します。
◎STEP2:新しいコーピングを追加する
コーピングは、質より量が重要です。日常の中でできる、ちょっとしたコーピングをたくさん見つけましょう。尊敬する人や小説の登場人物ならどうするかを想像しながら考えてみるのもアイデアが広がり、楽しみながら取り組めます。誰かに話を聞いてもらったり、手伝ってもらったりするなど、周囲にサポートを求めることも、大切なコーピングの1つです。
◎STEP3:リストを作成し、ストレスを感じたら実践する
STEP1、2で書き出したコーピングの方法をリスト化し、いつでも持ち歩けるようにします。カードやスマホのメモ機能などを使用するとよいでしょう。そして、ストレスを感じたらリストのコーピングを実践し、効果を観察します。
このような実践と観察を続けると、「このストレスには、Aのコーピングより、Bのコーピングが効果的」といった自分なりの使い方のコツがつかめてきます。
3.コーピングを企業で導入する
(1)従業員の対処スキルの向上
セルフケア研修や管理者研修など、従業員の教育・育成プログラムにコーピングを導入するのも1つの方法です。
ストレスは、ライフステージ(結婚など)や、キャリアの発達段階(昇進など)に応じて変化します。環境や立場の変化がどのようにストレスに関わってくるのかを考慮して、コーピングも見直す必要があります。
研修は、キャリアの節目ごとなど、定期的、継続的に学べるよう計画的に実施すると効果的です。
(2)ラインケア力の向上
管理者、人事・総務担当者がコーピングを学んでおくことで、部下の不調に気付きやすくなり、適切なラインケア(管理者による部下のケア)につながりやすくなります。
また、ラインケアでは、ケアを担う管理者を組織がサポートすることも重要です。ケアを担う人が健康でなければ、他者のケアは担えません。管理者が自身のセルフケアを行えるよう、研修の機会を提供したり情報提供をしたりすることや、対応に悩んだときに相談できる窓口や仕組みを整備するといったバックアップも重要です。
(3) 職場環境の整備
職場環境を見直し、従業員が日常的にコーピングをしやすい環境を整備することも重要です。
たとえば、コーピングの1つである「相談する(サポート希求)」に着目して、相談窓口の設置、定期面談の実施など、従業員が相談しやすい環境を整えましょう。
業務遂行のストレス対処に必須となる問題焦点型コーピングは、「タスクを管理すること」「課題を整理し解決に向けたプランを立案すること」「関係者と連携すること」といった複数のコーピングが関わります。
そのため、1on1、メンター制度など、業務遂行における問題解決のプロセスを丁寧にサポートする仕組みを整えることが、職場環境の整備につながります。
日本実業出版社のウェブサイトはこちら https://www.njg.co.jp/
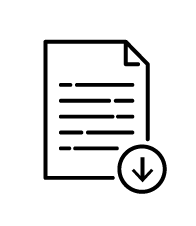
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




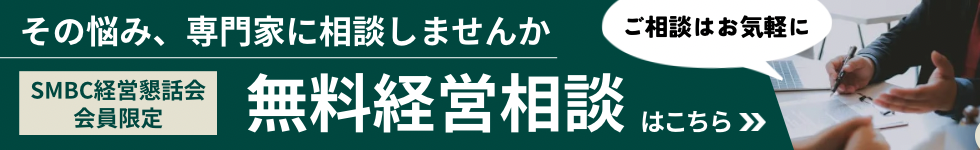

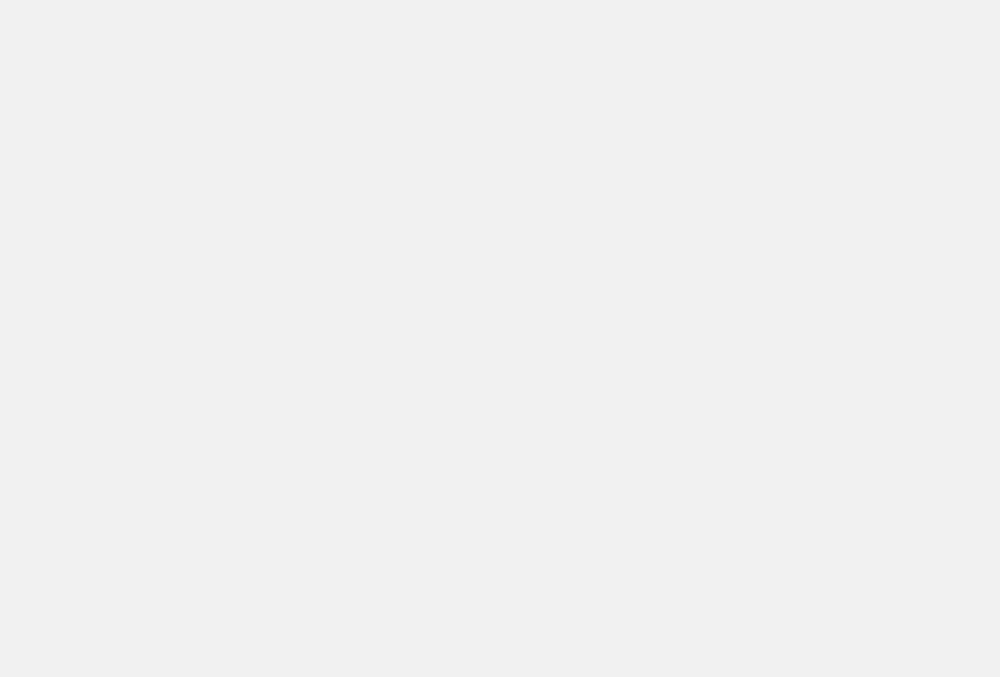

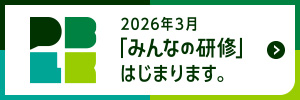




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
