Netpress 第2462号 判断のポイントは? メンタル不調社員の休職・復職に関する実務対応
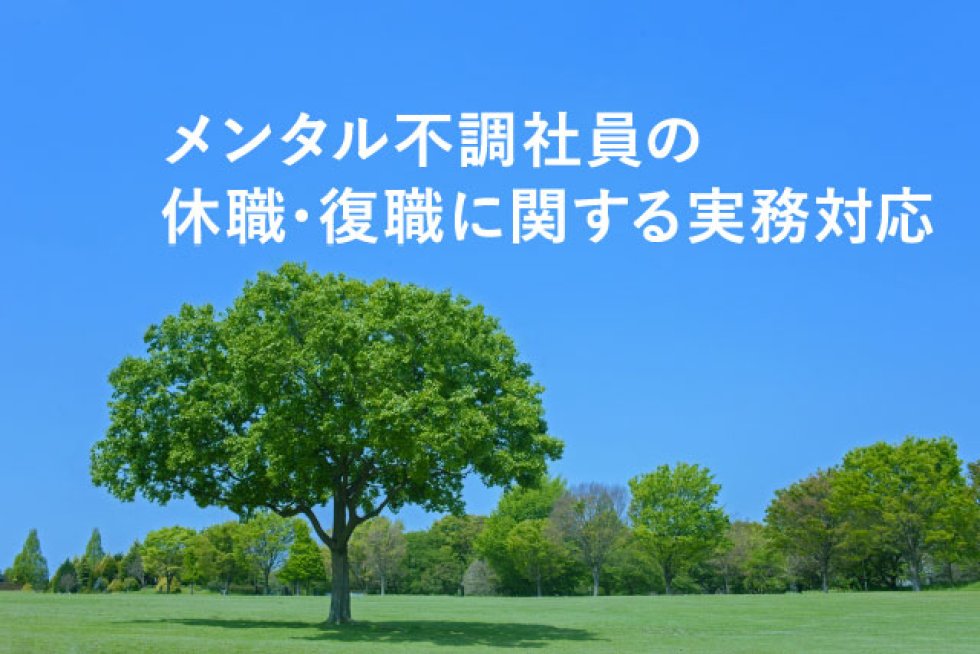
1.近年、メンタル不調者の増加に伴い、休職者も増加していますが、休職の内容等について法律上の規定はなく、制度は自由に設計することが可能です。
2.社員がメンタル不調になった際の、休職復職の判断のポイント、産業医との連携方法、就業規則を制定する際に気をつけるべきことについて解説します。
1.休職に関連する法律の基礎知識
近年、メンタル不調者の増加に伴い、休職者も増加しています。
「休職」とは、ある労働者について労務に従事させることが不能、または不適当な事情が生じた場合に、使用者がその労働者に対して、労働契約関係そのものは維持させながら、労務への従事を免除することまたは禁止するものであるとされています。
意外かもしれませんが、休職の内容等について法律上の規定はありません。
休職制度を定めるか定めないかというところから各使用者の自由となっています。
休職制度を採用して就業規則に定める場合であっても、その内容や制度は、それぞれの事業内容に応じて自由に設計されます。
休職事由としては、次のようなものがあります。
- 「傷病休職」
- 「事故欠勤休職」
- 「起訴休職」
「傷病休職」は、業務外の傷病による長期欠勤が一定期間に及んだときに行われる休職で、休職期間の長さは勤続年数などに応じて決められることが多いようです。
もちろん、その後に傷病から回復して労務提供が可能になれば休職は終了します。本稿のテーマである「メンタル不調による休職」も、まさにこの傷病休職の枠組みにおける休職です。
なお、休職命令を発令する際には、就業規則上の休職事由への該当性が重要になります。休職事由をある程度具体的に設定するとともに、包括条項(バスケット条項)も準備しておくとよいでしょう。
2.メンタル不調と休職命令について
「メンタル不調」は、正式には「メンタルヘルス不調」といいます。
メンタルヘルスとは、心の健康状態、精神的な健康状態のことをいいますが、それが不調にある状況が「メンタルヘルス不調」ということになります。
就業規則等の内容にもよりますが、メンタル不調の状態が続き、就業規則に定める傷病休職事由に該当する場合に、使用者から休職命令が発令され、休職が開始されることになります。
骨折やがん等の身体疾患のため労務が提供できなくなる状態と、うつ病等の精神疾患(=メンタル不調)のために労務が提供できなくなる状態は、傷病のために労務が提供できないこと、治療・療養を優先する必要があることなどで大きく共通しています。
もっとも、近年では、メンタル不調の療養のために相当期間休職する者が増加しています。
傷病名としては、適応障害、うつ病(=気分障害)などが多く見られますが、その背景に、発達障害等の合併が指摘されるケースも増加傾向です。
3.復職の際の注意点
心身の不調が改善して治癒し、労務提供ができるようになれば復職となりますが、身体の傷病とは違って、精神の傷病は「治癒」したかどうかの判断が難しいのが特徴です。
また、骨折等の傷病では、再度ケガなどをしない限り、順調に職場復帰が進んでいくことが通常ですが、メンタル不調の場合は、復職後に症状が再燃したり、メンタル不調が再発・増悪したりするなどして、短期間で再度の傷病休職に至ることも少なくありません。
そうすると、次のような点について根拠をもって判断するプロセスが大切になります。
| ・そのメンタル不調が本当に「治癒」しているか |
| ・復職後に十全な労務提供が可能であるか |
| ・復職後にストレスに負けてメンタル不調を再燃させないか |
ここでポイントになるのが、主治医が作成する「復職可否の診断書」をどう評価するかという点です。
一般的には、まず、復職を希望する労働者が「復職が可能である」とする主治医の診断書を取り付け、使用者に提出します。
その後、使用者によって復職の可否が判断されますが、主治医の判断をそのまま鵜呑みにしないように気をつける必要があります。
というのも、主治医は医療機関でしかその患者(労働者)と接しませんし、その患者の労務提供の実際を熟知するものでもないからです。
そのため主治医は、患者から「もう大丈夫です。仕事に戻れそうです」という申告を受けると、「復職可能」という内容の診断書を書くことが多くあります。
そうすると、主治医の診断書をそのまま真に受けて復職を許可したものの、実際にはメンタル不調が十分に改善しておらず労務提供が十全にできないということや、メンタル不調が再発・増悪してしまうといった事態がしばしば起こってしまうのです。
丁寧な対応としては、当該労働者の許可を得たうえで、人事担当者が主治医とコミュニケーションをとり(面会や電話など)、主治医に具体的な労務内容の情報を提供するなどして、復職についてより正確な判断をしてもらうようにするとよいでしょう。
また、職場において労働者の健康管理等を効果的に行うために産業医を選任している場合は、積極的に対応をしてもらいましょう。
産業医に、主治医の作成した診断書を分析してもらい、労務提供が可能な状況であるのかどうか、メンタル不調が再発・増悪しないかどうかについて、専門的なアドバイスを受けることもよいと思います。
◎協力/日本実業出版社
日本実業出版社のウェブサイトはこちらhttps://www.njg.co.jp/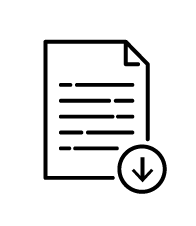
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan




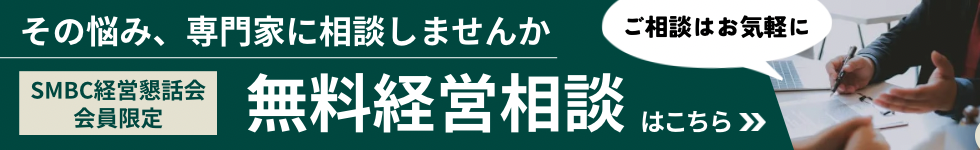

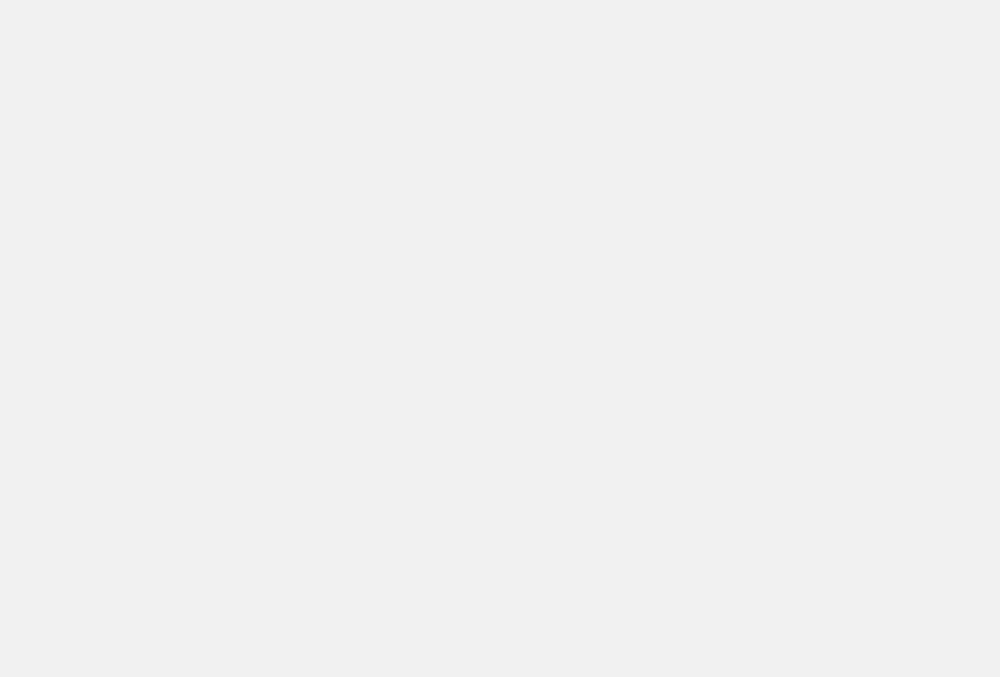

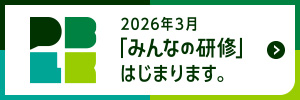




 InfoLoungeとは
InfoLoungeとは ログインでお困りの方
ログインでお困りの方
